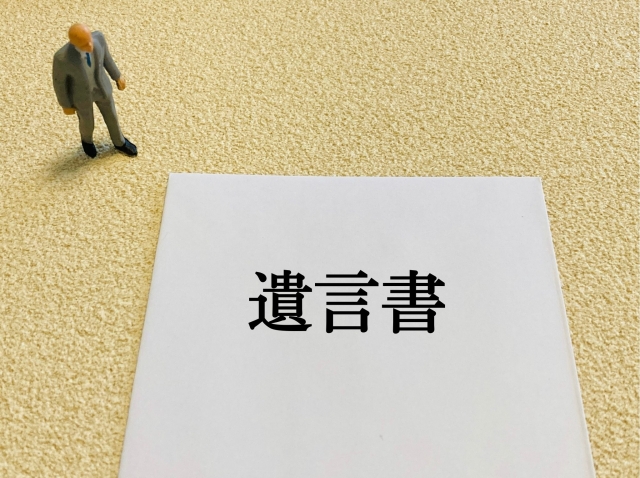遺言書の基本から3つの方式の違い、効力、書き方、注意点、法務局の保管制度までを解説します。初めての方でも安心して準備が進められるよう、必要な情報をわかりやすくまとめました。
遺言書とは、自分が亡くなった後に「財産を誰にどのように引き継ぐか」を示す重要な書面です。きちんとした遺言書があれば、相続をめぐるトラブルを防げて、家族に自分の意思を正しく伝えられます。
一方で、方式や記載方法を誤ると無効になる可能性もあるため、正しい知識が必要です。
本記事では、遺言書の基本から種類ごとの特徴、具体的な書き方や注意点、さらには2020年に始まった法務局での保管制度まで、初心者の方にも理解しやすく解説していきます。
遺言書とは
遺言書とは、自分が亡くなった後に「どの財産を、誰に、どのように引き継ぐか」を明記するための書面です。民法第960条では、遺言は法律で定められた方式に従わなければ効力がないと定められており、法的に有効な遺言書を作成するには、一定の要件を満たす必要があります。
遺言書は、生前に築いた財産や思いを、自分の意思に基づいて確実に伝えるための重要な手段です。たとえば、子どもがいない夫婦や、内縁関係にあるパートナー、事実上の介護を担ってきた相続人以外の親族など、法定相続では希望通りに財産を渡せない場合でも、遺言書があればそれが可能になります。
また、法定相続では相続人の話し合いによって財産の分割方法を決めなければいけません。しかし、遺言書が存在すれば、その内容に従って相続手続きが進められます。そのため、不要なトラブルや感情的な争いを未然の防止にもつながります。
このように、遺言書は単なる財産の分配指示書ではなく、相続の円滑な実行と家族間の平穏を守るための“最後の意思表明”ともいえる存在です。
法定相続との違い
法定相続とは、遺言書がない場合に法律の定めに従って遺産を分ける制度です。相続人の範囲や配分は、民法に明確に規定されています。たとえば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者が1/2、子どもが1/2を法定相続分として取得するのが原則です。
しかし、法定相続はあくまで法律が定めたモデルケースによる配分であり、個別の家庭事情や本人の想いは考慮されません。内縁関係の配偶者や世話になった友人・知人などは法定相続人には含まれず、法律上の遺産の取り分は一切ありません。
遺言書の3つの種類
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれに特徴や作成手続き、保管方法、費用、リスクなどが異なります。
各遺言書の違い、メリット・デメリットをわかりやすく比較しながら解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、最も一般的で手軽な遺言書です。本人がすべて自筆で作成します。費用をかけずに作成できる一方で、法的要件の不備による無効リスクや、紛失・改ざんの可能性にも注意が必要です。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。財産目録だけはパソコンや代筆での作成でも問題はありません。ただし、すべてのページに署名と押印が必要です。書式が自由な反面、法律に沿って正しく書かれていないと無効になります。
2020年7月からスタートした法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書の紛失・改ざんリスクを防ぎ、検認も不要になります。費用は1通あたり3,900円(保管申請手数料)で、法務局での申請・本人確認・形式確認が行われます。
【参照】
法務省/自筆証書遺言書保管制度について
メリット
- 手数料がかからず、自宅で手軽に作成できる
- 誰にも知られずに作成・保管できる
- 書き直しや修正も自由に行える
デメリット
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
- 相続開始後、家庭裁判所で検認が必要になる
- 法的要件を満たさないと無効になる可能性がある
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、最も法的信頼性が高い遺言書です。公証人が関与して作成されます。作成には費用がかかるものの、無効になるリスクがほとんどなく、遺言内容を確実に実現したい人に適しています。
公証役場に出向き、公証人と証人2名の立会いのもとで内容を口述し、公証人が文書を作成します。完成した遺言書は公証役場で保管され、正本・謄本が交付されます。
メリット
- 無効リスクが極めて低い
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんの心配がない
デメリット
- 作成に手間と費用がかかる(財産額により数万円〜十万円程度)
- 証人2名の立会いが必要(身内は原則不可)
- 内容が公証人や証人に知られるため、秘密性は低い
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言の存在だけを公証役場で確認・保管する方法です。ただし、実務上の利用は少なく、他2種類と比べて中途半端な性質を持ちます。
遺言書の内容を自筆または代筆・パソコンなどで作成し、封筒に入れて封印します。公証人と証人2名の前で封印された遺言書が自分のものであることを申述し、公証人がその旨を封書に記載します。遺言内容自体は公証人も確認しません。
メリット
- 内容を誰にも知られずに作成・保管できる
- 代筆やパソコンでの作成が可能
デメリット
- 相続開始後、家庭裁判所の検認が必要
- 遺言の内容に不備があっても公証人が確認しないため、無効となるリスクが高い
- 作成手続きが煩雑で利用者は少ない
遺言書を作成するメリット4選
遺言書は相続に関するトラブルを回避し、自分の意思を正確に伝えるための有効な手段です。遺言書を作ることで得られる主なメリットについて詳しく解説します。
1. 相続トラブルが回避できる
遺言書があることで誰にどの財産を分けるのかが明確になり、相続人同士の意見の食い違いによる争いを未然に防げます。法定相続人が複数いる場合、話し合いがまとまらず調停や裁判に発展することも珍しくありません。遺言書を作成しておくことで、このような対立のリスクを大幅に軽減できます。
2. 相続手続きをスムーズに進められる
遺言書、とくに公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が不要です。これにより、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きが早期に完了する可能性が高まります。
3. 特定の人へ遺贈できる
法定相続人以外にも財産を渡せるのが遺言書の特徴です。たとえば内縁の配偶者、事実婚のパートナー、長年介護してくれた親族などにも、自分の財産を遺贈できます。民法上の相続権がなくても、遺言によって受け取らせられます。
4. 自分の意志を明確に遺せる
相続財産の分配だけでなく、葬儀の方法やペットの世話、遺品整理の指示など、死後の希望を記せます。
家族への感謝の言葉など、法的効力はなくても気持ちを伝えるメッセージとして活用される方も少なくありません。
遺言書を作成する際の4つの注意点
遺言書は作成方法を誤ると法的に無効になるリスクもあり作成するにあたり、いくつか注意点が存在します。遺言書を作る際に考慮すべきリスクについて詳しく解説します。
1. 法的要件を満たさないと無効になる
自筆証書遺言は全文を自筆で書き、日付・署名・押印がなければ法的に無効となります。
また、内容が不明瞭だったり、第三者に解釈を委ねるような曖昧な表現だったりするとトラブルの原因となります。書き留める内容は誰が読んでも明確な文章であるよう、注意しましょう。
2. 遺言書の紛失や改ざんのリスク
自宅で保管する自筆証書遺言は、紛失・破棄・改ざんなどのリスクがあります。こうしたリスクを避けるには、公正証書遺言または法務局の自筆証書遺言保管制度の利用が有効です。
3. 遺言内容によっては争いの火種になる
たとえば「長男に全財産を相続させる」のような一方的な内容だった場合、他の相続人が感情的に不満を抱くケースがあります。事前に家族に遺言の趣旨を伝えたり、説明文を添えたりして、不要な対立を避ける工夫が求められます。
4. 遺留分への配慮が必要
法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されており、それを侵害する内容の遺言は遺留分侵害額請求の対象となります。その結果、遺言どおりに相続が行われないケースもあります。そのため、作成時には法的な確認が重要です。
緊急時専用の特別方式遺言とは
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の普通方式以外に、緊急時専用の特別方式遺言という遺言方法が民法で認められています。
特別方式遺言とは、緊急時・隔絶状態における例外的な遺言方式です。災害や戦争などの非常時や、死が差し迫った状況で通常の遺言方式が使えない場合に限って認められる特例です。特別方式遺言には、以下の2つの分類があります。
死亡危急者遺言
死亡危急者遺言とは、命の危険が迫る場面で認められる遺言です。事故や重篤な病気などで、死の危険が切迫している場合、口頭で遺言の内容を伝えられます。
死亡危急者遺言は、命を失うリスクがあるごく限られた状況でしか認められません。仮に回復した場合は、速やかに普通方式での遺言書作成をする必要があります。
隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、船舶・僻地など連絡手段が限られる場合に認められます。戦争・航海中・伝染病で隔離された施設など、外部と隔絶された環境で行う遺言方法です。
信頼できる遺言書を遺そう
遺言書は、自分の最終意思を法的に残すための重要な書面です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式はそれぞれ使い分けが可能で、最新制度の導入により選択肢も広がっています。
作成時には方式の要件や修正ルールを守り、遺留分への配慮も忘れずに行いましょう。特にトラブル回避と確実性を重視するなら、公正証書や法務局保管を選ぶと安心です。
人生の終幕を見据えて、財産配分や想いをしっかり“かたち”にしておくことが、残される家族への最大の贈り物となるでしょう。