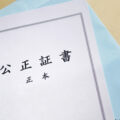遺言書で一人に全財産を相続させることは可能です。一人に全財産を相続したい際の遺言書の書き方や注意点などを詳しく解説します。
遺言書とは、「財産をあの人に渡したい」という想いを実現するためのものです。相続人が複数いる場合でも、遺言書を使えば一人に全財産を渡せます。ただし、確実に一人に相続させるためには形式の不備や法的リスクに注意しなくてはいけません。
本記事では、遺言書で全財産を特定の一人に相続させるための正しい書き方やトラブルを防ぐためのポイントまで解説します。
遺言書があれば全財産を一人に相続させられる
相続において、最も優先されるのは被相続人の意思です。そして、遺言書は被相続人の意思を明確に示す手段です。民法第902条でも、遺言がある場合はそれに従って相続が行われると定められています。
つまり、遺言書があれば法定相続人の人数や相続割合に関係なくその内容が第一に尊重されるのです。「長男に全財産を相続させる」と記されている場合、それが適切な形式で作成された遺言書であれば有効です。
原則、誰にどれだけ渡すかは自由
法律上、原則として財産は築いた本人が自由に処分できる権利が認められています。そのため、法的にも相続人のうちの一人にすべての財産を渡すといった内容の遺言書も可能です。ただし、遺言書の形式や内容に不備があると、無効になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
全財産を一人に相続させるケースでは、「全財産を長男に」「特定の孫に」などと記載されることが多いです。遺言書には「相続させる」と明記することが重要です。曖昧な表現を避けることで後々のトラブル防止にもつながります。
ただし、遺言書の内容が他の相続人にとって不公平に感じられる場合、異議を唱えられる可能性もあります。そうならないためにも、配慮が求められます。
法定相続と異なる分配を希望する場合、遺言書が必須
遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続分に従って分割されます。
配偶者と子どもがいる場合は配偶者が2分の1、子どもが残りを等分で受け取ります(民法第900条)。そのため、「すべての財産を妻に渡したい」といった希望がある場合、遺言書がなければその意思は反映されません。つまり、法定相続と異なる分配を望む際は遺言書の作成が必須となります。特に不公平を感じ取られやすい一人の相続人に集中して遺産を渡したい場合は、その意図をはっきりと文章に残しておくことが重要となります。
全財産を一人に相続させる際の3つの注意点
全財産を一人に相続させることは法律上可能ではあるものの、注意したいポイントがいくつかあります。代表的な注意点を3つお伝えします。
1. 他の相続人に遺留分があることへの配慮
全財産を特定の一人に相続させる場合、最も注意すべきなのが遺留分の存在です。遺留分とは法律で認められた最低限の取り分のことを指し、相続人に保障されています。民法第1042条に基づき、遺留分の対象となるのは、配偶者や子ども、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば、子どもが2人いるケースで「長男に全財産を相続させる」と遺言した場合、次男には遺留分として全財産の4分の1の請求権が発生する可能性があります。遺言書の内容が遺留分を侵害していると、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされ、相続後にトラブルになることがあります。
2. 相続トラブルが発生する可能性がある
「一人にすべて相続させる」という遺言内容は、他の相続人の反感を招きやすいものです。特に、生前の関係が希薄だった親族が「なぜ自分には何もないのか」という不満を爆発させるケースは少なくありません。このような心理的な反発から、遺言書の有効性を争う遺言無効確認訴訟や調停へと発展するケースも珍しくないのです。
相続トラブルは時間も労力もかかり、遺された人々の関係を深く傷つけます。そのため、一人に相続させたい場合は「なぜその人にすべてを託すのか」といった思いを、生前にきちんと説明しておくことでトラブルを回避しやすくなるでしょう。また、公正証書遺言のような客観性の高い形式で遺言書を作成することで、争いのリスクを減らせます。
3. 遺言の形式不備により無効になる恐れがある
遺言書はただ書けばよいというものではありません。法的に有効な形式で作成されていないと、せっかく遺した遺言書でも無効になるリスクがあります。
たとえば自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自筆で書く必要があり、日付・署名・押印も必須です(民法第968条)。要件にひとつでも不備があると遺言書は無効と判断され、法定相続通りに財産が分配されてしまいます。
特に高齢者の場合、筆跡が不鮮明であったり、日付の記載が曖昧だったりすることで遺言書の効力が否定されるケースもあります。そのため、不備のないよう十分に注意し、可能であれば専門家のリーガルチェックを受けておくと安心です。
相続人の遺留分の確保が必要
遺留分とは、特定の相続人に法律で認められた最低限の財産の取り分です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、相続人はその分の請求ができます。
遺留分を請求できるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子ども(直系卑属)
- 父母などの直系尊属(※子どもがいない場合に限る)
遺留分の割合は、次のとおりです。
- 相続人全体の法定相続分の1/2
- 直系尊属のみが相続人の場合は1/3
遺留分侵害額請求とは?
遺留分が侵害された場合、対象となる相続人は遺留分侵害額請求を行えます。遺留分侵害額請求とは相続財産の返還を求めるものではなく、侵害された金額の支払いを請求するという制度です。
遺留分侵害額請求は、相続が開始し、かつ遺留分の侵害を知った日から1年以内に行う必要があります(民法1048条)。この期間を過ぎてから請求しても、請求権は時効によって消滅してしまうため注意が必要です。
たとえば、長男に全財産を相続させる遺言書があった場合、次男が自分の遺留分を主張して金銭を請求してくるケースがあります。遺留分の主張が認められれば、長男は遺言通りに全財産を受け取った後でも、次男に一部の金額を支払わなくてはいけません。
遺留分対策としてできること3選
遺留分を巡るトラブルを避けるためには、生前に対策をしておくことをおすすめします。対策としてできる3つのポイントをお伝えします。
1. 事前に説明しておく
遺留分対策として最も基本的で効果的な対策は、相続人に対して生前に意向の説明しておくことです。「なぜ一人に全財産を託すのか」「他の人に渡さない理由は何か」を冷静に伝えることで、そのほかの相続人からの納得を得やすくなります。感情的な衝突を避けるには書面だけでなく、家族会議といった場で意思を共有するのが望ましいでしょう。
2. 遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てる
相続人にあらかじめ遺留分を放棄してもらう方法もあります。ただし、これは口約束では無効です。家庭裁判所で正式に許可を得る手続きが必要です(民法1049条)。
ただし、この方法は現実的には難易度が高く、慎重な対応が求められます。これを機に家族間の仲が悪くなってしまう最悪のケースも想定し、なるべく波風の立たない伝え方を意識しましょう。
3. 生前贈与を活用する
生前贈与を活用し、財産の一部をあらかじめ移転しておく方法もあります。
ただし、相続開始前の一定期間内の贈与は遺留分計算の対象に含まれるため注意が必要です(民法1044条)。
全財産を一人に相続する場合は準備と配慮が重要
法律上、遺言書を作成することで全財産を特定の一人に相続させることは可能です。原則として、明確な意思を遺言書で残しておけば、法定相続とは異なる分配もできます。
しかし、そのためには遺留分への配慮や遺言の形式的な正確さ、他の相続人との関係性に注意が必要です。相続のタイミングで遺族を思わぬトラブルに巻き込まないためには、書き方の正確さと気持ち伝え方がカギとなります。
大切な財産を心から信頼する相手に遺すためには、早めに準備を始めるに越したことはありません。公正証書遺言の活用や専門家への相談など、適切な手段を取り入れながら、自分の意思をしっかりと形にしておきましょう。
あんしん祭典では終活トータルサポートを提供しています。相続や遺言に関するアドバイスはもちろん、介護施設の紹介やエンディングノートのプレゼントも可能です。
LINEで気軽に終活の相談ができるサービスです。簡単30秒で登録できるので、終活や相続にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。