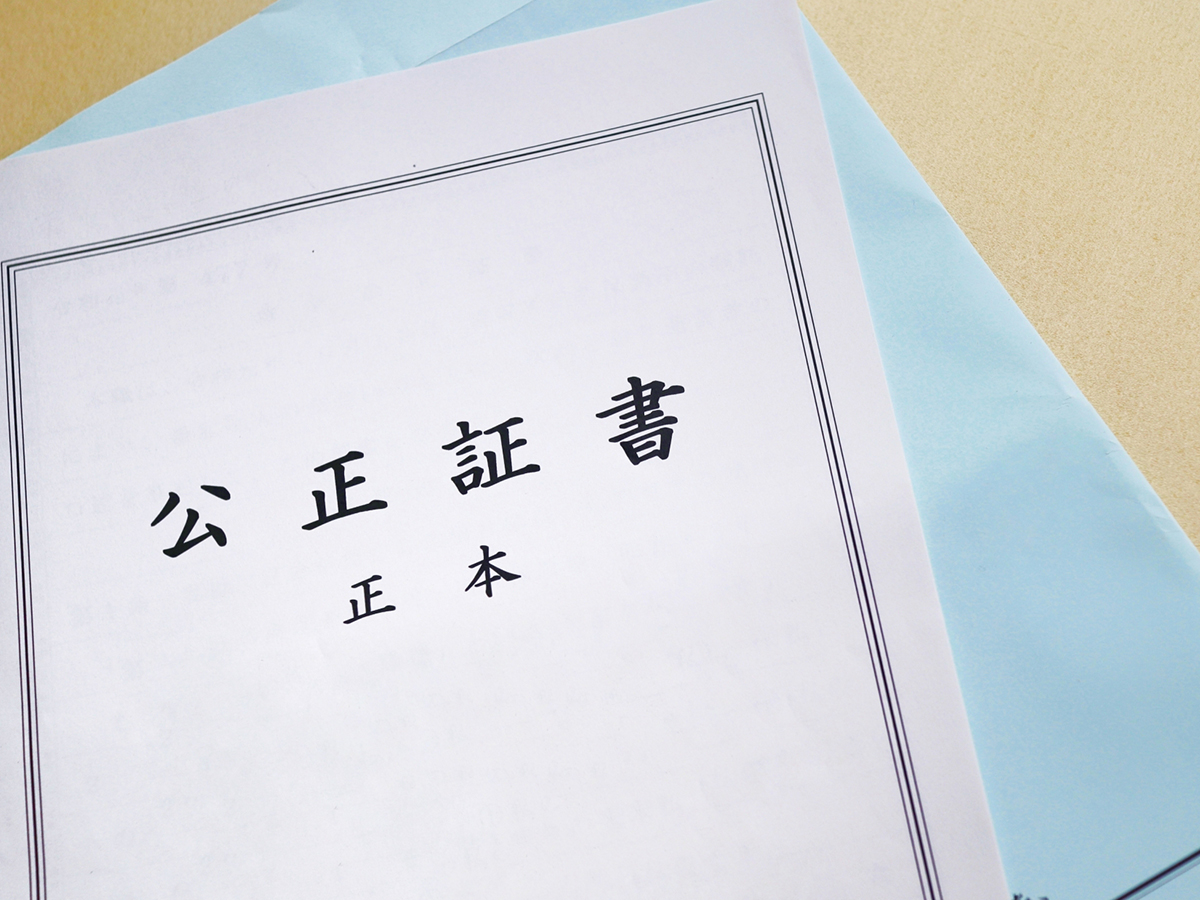遺言書には、一般的に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ特徴や費用、メリット・デメリットなどが異なります。遺言書の3つの種類の違いを、わかりやすく解説します。
もしものときに備えて遺言書を残したいものの、どのように書けばいいのか迷う方は少なくないでしょう。遺言書には3つの形式があり、それぞれ作成方法や効力、保管方法に違いがあります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類のそれぞれの特徴や注意点を解説します。
遺言書とは
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように渡すかを明確に伝えるための大切な書類です。残された家族が遺産分割で揉めないように、故人の意思を法的に残す手段として活用されます。
日本の相続では、遺言がないと民法に基づいた法定相続によって遺産が分配されます。しかし、それでは自分(故人)の希望とは異なる相続が実行される可能性があります。法定相続人ではない内縁の配偶者や特別に世話になった人に財産を残したい場合、遺言書がなければ希望は反映されません。
また、遺言書を作成しておくとあらかじめ誰に何を相続するのかを決めておけます。そのため、誰が何を相続するのかを巡る相続人同士のトラブルを未然に防げます。
このように遺言書にはさまざまな役割があり、近年遺言書の準備の重要性が高まっています。
遺言書には3つの種類がある
日本の法律では、遺言の方式は大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の2つに分類されます。
事前に準備をする場合、日常的に使われる普通方式遺言の方式に沿って遺言書を作成します。普通方式遺言書には、次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
3種類の遺言書は、それぞれ作成方法、効力、保管方法に違いがあります。どの形式を選ぶかによって、将来の相続に大きな影響を及ぼすため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
普通方式遺言書に対して、特別方式遺言は災害時や死期が迫った場合など、特別な状況下で認められる臨時的な形式です。たとえば、船に乗っている最中の航海中遺言や、病床で死を目前にした人が口頭で遺言する危急時遺言などです。
特別方式遺言はあくまで例外的な手段であり、多くの人にとっては普通方式の遺言書が現実的な選択肢となるでしょう。
普通方式遺言書の3つの種類
普通方式遺言書(以下、遺言書)には、3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。それぞれの特徴や作成方法、メリット・デメリットをそれぞれ解説していきます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が紙に全文を手書きして作成する形式の遺言書です。公的な手続きや費用がかからず、思い立ったときにすぐに書ける手軽さが最大の特徴です。家庭内で簡単に書き残せるため、特別な準備が必要ありません。誰にも内容を知られずに作成できるため、プライバシー性も高いといえるでしょう。
ただし、その自由度の高さゆえに法律で定められた要件を満たしていないと無効になるリスクもあります。そのため、正確な知識を持ったうえでの作成が重要です。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、次の要件をすべて満たす必要があります(民法第968条)。
- 遺言書の全文を自筆で記載する
- 作成した日付を明記する(例:「令和〇年〇月〇日」)
- 氏名を自署し、押印する
自筆証書遺言を作成する際、以前はすべてを手書きで書く必要がありました。
しかし、2020年の民法改正以降は条件が緩和され、財産目録の部分のみパソコンで作成したものや通帳のコピーでも良いとされています。ただし、一部をパソコンで作成した場合でも各ページに署名と押印をする必要があります。手間を省きすぎると無効の原因になるため、注意しましょう。
また、形式を少しでも間違えるとせっかくの遺言が無効になる可能性があります。記載漏れや不備がないよう十分注意しましょう。
自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言には、見つけてもらえない、改ざんされる、紛失するなど、保管面でのリスクが伴います。これらの自筆証書遺言のリスクを解消するために、2020年7月より法務局による自筆証書遺言保管制度が設けられました。
自筆証書遺言保管制度を利用すると、遺言書を全国の指定法務局で安全に保管してもらえます。遺言者の死亡後は相続人などが保管の有無を確認できるシステムが整っており、家庭裁判所での検認も不要になるというメリットがあります。
法務局に保管を依頼するためには、事前に予約のうえ本人が出向く必要があります。手数料は1通につき3,900円です。(令和7年7月時点)
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言書のメリットとデメリットをそれぞれポイントでお伝えします。
〈メリット〉
- 費用がかからない
- ひとりで作成できる
- 思い立ったときにすぐに書ける
- 法務局で保管すれば安全性も高まる
〈デメリット〉
- 法的要件を満たしていないと無効になる
- 自宅で保管した場合、発見されない・紛失する可能性がある
- 内容に誤解が生じやすい
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が遺言内容を聞き取り、文書として作成する形式の遺言です。自筆証書遺言とは異なり、専門家が作成に関わります。そのため、形式不備で無効になる心配がほぼありません。
また、原本は公証役場に保管され、万が一自宅の写しを紛失しても再発行が可能です。
確実性と安全性の高さから、トラブル防止の観点で最も信頼性のある遺言方式といえるでしょう。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成には遺言者本人が公証役場に出向き、公証人と面談する必要があります。また、証人2名の立会いが法律上義務付けられています(民法第969条)。証人は未成年者や推定相続人、その配偶者など一部の人はなれないため注意が必要です。
公正証書遺言の作成方法は次の通りです。
- 遺言内容の事前整理
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公証役場に出向き、証人の立会いのもとで作成・署名・押印
- 正本・謄本の受け取り
公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言は、作成にあたって財産額に応じた手数料が発生します。
費用はかかるものの、内容の正確性と安全性を考えるとコストパフォーマンスの高い方法といえるでしょう。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言書のメリットとデメリットをそれぞれポイントでお伝えします。
〈メリット〉
- 無効になる心配がほぼない
- 原本は公証役場が保管するため、紛失や改ざんのリスクがない
- 検認手続きが不要で、相続の手続きがスムーズ
- 出張対応も可能
〈デメリット〉
- 手数料や証人費用など、費用がかかる
- 公証役場に出向く必要がある
- 証人2名の用意が必要
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも見せずに済む特徴があります。遺言者があらかじめ遺言書を作成して封をしたうえで公証役場に持ち込み、公証人と証人2名の前で「この封筒に遺言書が入っている」という事実を確認してもらいます(民法第970条)。
遺言の内容は公証人にも伝えないため、プライバシーが守られやすいのが大きなメリットです。ただし、自筆証書遺言同様、形式不備による無効のリスクがあるため注意が必要です。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言の作成には、遺言書の事前準備と封印の手続きが必要です。基本的な流れは次の通りです。
- 遺言書を本人が自筆またはパソコンで作成する
- 遺言書を封筒に入れて封印する
- 公証役場へ持参し、公証人および証人2名の立会いのもとで封印の確認をする
- 公証人は遺言書が存在することを証明する文書を作成し、封筒に署名・押印
秘密証書遺言では、封印の確認はありますが内容のチェックはされません。法律上の要件を満たしていない場合、相続時に無効とされてしまう場合があります。
秘密証書遺言のメリットとデメリット
秘密証書遺言書のメリットとデメリットをそれぞれポイントでお伝えします。
〈メリット〉
- 内容を誰にも知られずに作成できる
- パソコンで作成可能
- 公証人による形式的な確認で、遺言の存在を公的に証明できる
〈デメリット〉
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 自宅保管のため、紛失・改ざん・発見されないリスクがある
- 証人2名の立会いが必要
- 実際の利用者が非常に少ない
- 家庭裁判所での検認が必要
自分に合った遺言書の種類を選ぼう
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの普通方式と、緊急時などに限定的に利用される特別方式遺言があります。それぞれの方式には、手軽さ・費用・安全性・プライバシー性などにおいてメリットとデメリットが存在するため、目的や状況に応じて、最適な形式を選びましょう。
遺言は、非常に有効な終活のひとつです。元気なうちにしっかりと意思を形にしておくことで、自分の想いをきちんと伝えられ、残された家族も安心して相続手続きを進められます。迷ったときや不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
あんしん祭典では終活トータルサポートを提供しています。相続や遺言に関するアドバイスはもちろん、介護施設の紹介やエンディングノートのプレゼントも可能です。
LINEで気軽に終活の相談ができるサービスです。簡単30秒で登録できるので、終活や相続にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。