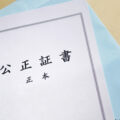生前墓とは、存命中に自分のために建てるお墓のことです。本記事では生前墓のメリット・デメリットや費用、購入の流れがわかります。終活を始めたい方や、家族に迷惑をかけたくないと考える方に向けた記事です。
生前墓とは、自分が元気なうちに建てるお墓のことです。亡くなったあとの準備を前もって整えておくことで、自分の希望を反映できるだけでなく、家族の負担を軽くする目的もあります。
しかし「生前にお墓を建てるのは縁起が悪いのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。終活の一環として前向きにとらえる人が増えている一方で、費用や手続きがわかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、生前墓のメリット・デメリットや費用、建てるときの注意点から購入の流れまで詳しく解説します。これから終活を始めようと考えている方や、自分らしいお墓を考えたい方は、ぜひ参考にしてください。
生前墓とは
生前墓とは、自分が存命のうちに建てるお墓のことです。あらかじめお墓を用意しておくことで、気に入った場所やデザインを自分で選べるほか、家族の負担を減らせるなどのメリットがあります。
少子化や高齢化が進むなかで、「元気なうちに身の回りを整えておきたい」と考える人が増え、生前墓を選ぶ方も年々多くなっています。終活の一環として関心を持つ人も少なくありません。
生前にお墓を建てるのは、むしろ縁起の良いこと
生前にお墓を建てることに対して、「縁起が悪いのでは」と感じる方もいるかもしれません。しかし実際には、生前墓はむしろ縁起の良いものとされています。
中国や日本では古くから、身分の高い人が自分のために立派なお墓を生前に用意する風習がありました。たとえば、聖徳太子も自らの墓を生前に建てたと伝えられています。生前に自分の死後の準備を進めることは功徳を積むことになるという考え方もあります。
こうした背景からも、生前墓は不吉なものではなく、むしろ「人生の締めくくりを丁寧に整える行動」として受け入れられてきたのです。
現代では終活の一環として、自分の意志でお墓を選ぶ人が増えています。死をタブー視せず、これからの人生を前向きに生きるための準備として、生前墓を建てることはごく自然な選択といえるでしょう。
生前墓のメリット
生前にお墓を建てることで得られるメリットは、想像以上に多くあります。精神的な安心感だけでなく、家族への思いやりや経済的な配慮にもつながる点が、生前墓を選ぶ人が増えている理由です。
ここでは、生前墓を建てることで得られるメリットを3つ紹介します。
自分のお墓を自分で選べる
生前にお墓を建てる最大のメリットは、自分の意思でお墓を選べることです。立地や景観、宗教的な要素、石のデザインまで、自分の好みに合わせて選択できます。
「こんな場所で眠りたい」「こんな形にしたい」といった希望がある方にとって、生前墓はその思いを形にできる手段です。自分らしい最期を迎えたい方には特におすすめです。
遺族の負担を減らせる
お墓の準備は、亡くなったあとの遺族にとって大きな負担となるでしょう。急な対応を迫られることも多く、精神的・経済的な負担は決して軽くありません。
生前にお墓を整えておけば、遺族はその後の手続きや費用の負担から解放されます。「家族に迷惑をかけたくない」と考える方にとって、生前墓は思いやりのある選択といえるでしょう。
相続税対策になる
お墓は相続税の課税対象にならないため、生前にお墓を購入することで節税につながる可能性があります。現金や不動産などと違い、「祭祀財産」として扱われるためです。
まとまった資金があり、将来的な相続を見据えている方にとっては、生前墓の購入は税金対策になります。税金面も意識しながら終活を進めたい方に適しています。
生前墓のデメリット
生前墓には多くのメリットがありますが、注意すべきデメリットもいくつか存在します。後悔なく選択するためにも、あらかじめ確認しておくことが大切です。
ここでは、生前墓を建てる際に考慮すべき主なデメリットについて説明します。
年間管理費がかかる
生前墓を建てると、完成したその年から管理費が発生します。これは墓地を維持するために必要な費用であり、支払いが長期にわたる点に注意が必要です。
長期間の費用負担に不安がある方や、将来の支払い継続が難しいと感じる方には、生前墓の選択は慎重に検討したほうがよいでしょう。
メンテナンスの手間がかかる
お墓は風雨にさらされるため、定期的な掃除や簡単な手入れが必要です。生前に建てた場合、その維持管理を長年にわたりしなければなりません。
遠方に住んでいる方や、体力的にお墓掃除が難しい方にとっては、管理の負担がかえってストレスになる可能性もあります。
生前墓を建てるときの注意点
生前墓は計画的に進めることで、多くの安心を得られるものです。しかし、いくつかの点に注意しないと、後のトラブルや負担につながる可能性もあります。
ここでは、生前墓を建てる際に押さえておきたい主な注意点を紹介します。
納骨や承継方法を事前に家族と話し合う
生前墓を建てたあと、誰が納骨し、どのようにお墓を継いでいくかは、あらかじめ家族と話し合っておく必要があります。継承者が不在だったり、意志が共有されていなかったりすると、後の対応が難しくなるためです。
こうした確認を怠ると、いざ納骨という段階でトラブルが起きたり、お墓を維持する人がいなくなったりする恐れがあります。
墓じまいへの備えも考えておく
将来的にお墓を管理する人がいなくなった場合に備えて、墓じまいの可能性についても視野に入れておくことが大切です。永代供養墓への改葬や、行政手続きの準備なども含めて考える必要があります。
墓じまいについて何も決めていないと、残された家族が判断に迷い、精神的・金銭的に大きな負担を抱えることになりかねません。
現地を見学したうえで建てる
お墓の立地やデザインなどは、パンフレットやWebサイトの情報だけで選ばず、必ず現地を見学してから決めましょう。実際に足を運ぶことで、周囲の環境や管理体制、アクセスのしやすさなどを直接確認できます。
見学せずに決めてしまうと、「思っていた雰囲気と違った」「通いにくくて後悔した」といったミスマッチが起こるリスクがあります。
遺骨がないと購入できないことがある
霊園や墓地の中には、すでに遺骨がある人でないと申し込めない場所もあります。生前墓として利用できるかどうかは、事前に確認が必要です。
確認を怠ると希望する場所に申し込めなかったり、契約直前に条件が合わないことが発覚して、計画が振り出しに戻るおそれがあります。
生前墓にかかる費用
生前墓を建てる場合、いくつかの費用が発生します。墓地の種類や立地によって金額は異なりますが、あらかじめどのような費用がかかるのかを把握しておくことが大切です。
ここでは、生前墓にかかる主な費用についてご紹介します。
お墓の購入費
お墓の購入費は、墓石の製作や設置にかかる費用です。使用する石の種類や大きさ、デザインによって価格は変わります。一般的には数十万円から100万円以上かかることもあります。
また、施工費や文字彫刻代、基礎工事費なども含まれるため、見積もりを取る際は内訳をよく確認しておくと安心です。
永代使用料
永代使用料とは、墓地を一定の区画として使用する権利にかかる費用です。土地を購入するわけではなく、あくまで使用権に対して支払います。
金額は霊園の立地や規模によって異なり、都市部では高額になる傾向があります。この費用は一括で支払うのが一般的です。
年間管理費
年間管理費とは、霊園や墓地の共用部分の清掃や植栽管理、設備の維持にかかる費用です。墓地によっては墓石周辺の簡単な清掃も含まれることがあります。
この費用は毎年発生するため、長期的な視点での負担を考えておく必要があります。支払いを滞らせると、使用権の取り消しや撤去の対象になる可能性もあります。
生前墓を購入する流れ
生前墓の購入には、いくつかのステップがあります。ここでは、生前墓を建てる際のおおまかな流れを紹介します。
1.家族・親族の理解を得る
まずは家族や親族に、生前墓を建てたいという意志を伝えましょう。自分の考えを丁寧に伝え、納骨や承継についても話し合っておくことで、後のトラブルを避けやすくなります。
特に、墓守を誰が引き継ぐのかは重要なポイントです。家族の理解と協力があってこそ、生前墓は安心して建てられます。
2.墓地や石材店を探す
次に、希望する地域や宗教・宗派に合った墓地を探します。同時に、墓石のデザインや費用の相談ができる石材店も選びます。最近ではインターネットで霊園や石材店の情報を調べることも一般的になっています。
気になる霊園が見つかったら、必ず現地を見学しましょう。アクセスの良さや管理状況、雰囲気など、実際に足を運ばなければわからないことも多くあります。
3.契約を結ぶ
霊園や石材店を決めたら、墓地の永代使用契約や墓石の施工契約を結びます。契約内容には使用規約や支払い方法、完成時期などが含まれるため、細かい部分までしっかり確認することが大切です。
この段階で、年間管理費やメンテナンスの方針についてもあわせて確認しておくと安心です。
4.お墓の引き渡しと開眼供養
お墓が完成すると、引き渡しとあわせて「開眼供養(かいげんくよう)」をするのが一般的です。これはお墓を守ってくれる仏様を迎え入れるための儀式で、お墓に故人の魂を入れるという意味合いがあります。
開眼供養は遺骨がなくてもできます。生前墓の場合でも、建墓の節目として行うことで、自分の墓に対する気持ちがより明確になり、心の整理や区切りにもつながります。家族とともに執り行えば、今後の供養について話し合う良い機会にもなるでしょう。
生前墓は縁起が良く、メリットも多い
生前墓は「縁起が悪い」と思われがちですが、実際には古くから長寿や子孫繁栄を願う前向きな行動として受け入れられてきました。自分でお墓を選べる、家族の負担を減らせる、相続税対策になるといった多くのメリットがある点も、注目されている理由のひとつです。
もちろん、年間管理費やメンテナンスの手間といった注意点もありますが、それらを理解したうえで準備を進めれば、安心して人生の締めくくりを迎えられます。自分の意志で納得のいく場所を選び、家族とも話し合いながら準備を進めることで、これからの人生をより前向きに歩んでいけるはずです。
あんしん祭典では提携しているお墓や納骨堂などがあり、お墓の紹介や永代供養の手配もできます。ほかにも、死後の行政手続きや遺品整理なども承っており、大切な人を亡くした方をトータルでサポートします。
互助会に入会し、葬儀費用を積み立てていくことも可能です。お墓選びで悩みがある方、互助会に興味がある方は、まずはお気軽にご相談ください。