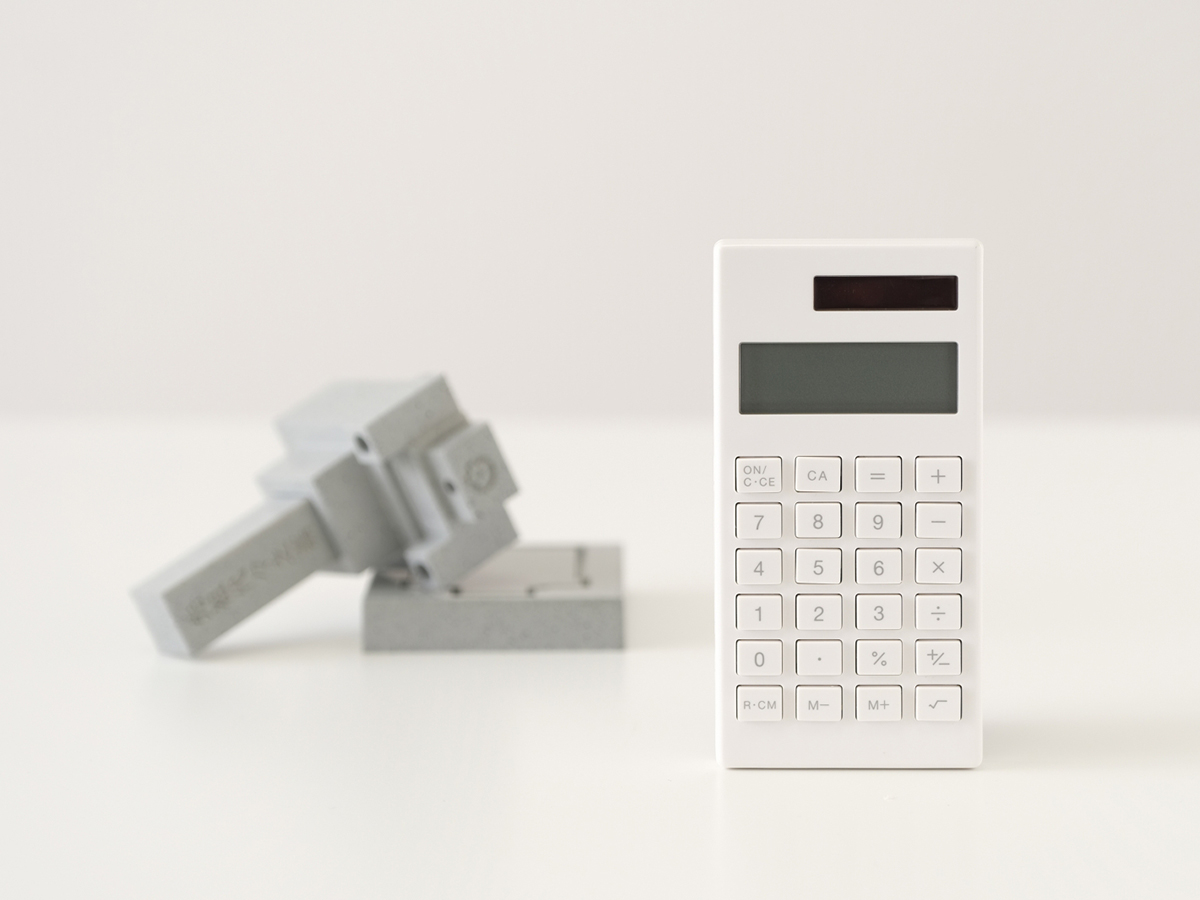無縁墓とは、管理する人がいなくなったお墓のことです。本記事では無縁墓が増えている背景や対策、無縁墓を墓じまいした後の供養方法がわかります。お墓の継承に不安がある方や墓じまいを検討中の方に向けた内容です。
無縁墓とは、お墓を継ぐ人や管理する人がいなくなり、放置された状態のお墓のことです。近年、この無縁墓が各地で増えており、社会問題としても注目されています。
「うちのお墓もいずれ無縁墓になってしまうのでは」と、不安を感じている方もいるかもしれません。家族に迷惑をかけたくないという思いや、先のことを考えて今のうちに準備しておきたいという方も多いでしょう。
本記事では、無縁墓とは何か、なぜ増えているのか、無縁墓になるとどうなるのか、そしてその対策としての墓じまいや新しい供養の方法について解説します。お墓の継承や供養について悩んでいる方、将来に備えて今できることを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
無縁墓とは
無縁墓(むえんぼ、むえんばか)とは、お墓の継承者や管理する人がいなくなり、供養や清掃などが行われなくなった状態のお墓のことです。墓地の管理者と連絡が取れなくなったり、使用料や管理料の支払いが途絶えたりすると、一定期間を経て「無縁墓」と判断されることがあります。
もともとは家族や子孫が代々守っていくことを前提に建てられたお墓ですが、さまざまな事情から後継者がいなくなり、誰からも手がかけられないまま放置されてしまうケースが少なくありません。
無縁墓が増えている理由
かつては家族や地域で守られてきたお墓ですが、近年ではさまざまな社会的変化によって管理が行き届かなくなり、無縁墓となってしまうケースが増えています。
ここでは、無縁墓が増加している背景として代表的な3つの要因を取り上げ、それぞれがどのように無縁墓の発生につながっているのかを解説します。
少子高齢化による後継者不足
日本では少子高齢化が急速に進んでおり、多くの家庭で子どもの数が減っています。そのため、実家のお墓を引き継ぐ人がいない、あるいは引き継げないという問題が各地で起こっています。さらに、親族がいても高齢であったり遠方に住んでいたりするため、実際にお墓を管理・維持するのが難しいケースもあります。
こうした後継者不足により、誰にも管理されないまま放置されるお墓が増え、結果として無縁墓となってしまうケースが後を絶ちません。
地域の過疎化による管理者不在
都市部への人口集中が進む一方で、地方では過疎化が深刻化しています。かつて多くの人々が暮らしていた地域でも、高齢化と人口減少によって墓地の管理者や利用者がいなくなる状況が各地で見られます。
こうした地域では、もともとあった共同墓地や寺院墓地の維持が困難になり、放置されたまま無縁化してしまうお墓が増えています。地元の住民も減っているため、草刈りや掃除といった最低限の管理すら行われず、無縁墓の増加につながっています。
「お墓を継ぐ」という意識の希薄化
近年は、家制度や宗教への帰属意識が薄れ、かつてのように「お墓を受け継いで守るのが当然」という価値観を持つ人が少なくなってきました。ライフスタイルの多様化や、宗教儀式に対する関心の低下もその一因です。
このような意識の変化により、たとえお墓を継ぐ立場にあっても「管理するつもりはない」「自分の代で終わらせたい」と考える人が増えています。その結果、お墓の継承が行われず、無縁墓として扱われる件数が増加しています。
無縁墓になるとお墓はどうなるのか?
お墓が無縁墓とみなされると、管理者である霊園や寺院などの判断により、一定の手続きを経て撤去されることがあります。具体的には、墓地の使用料や管理費の支払いが長期間滞り、かつ連絡が取れない状態が続くと、墓地の管理者は「無縁墓」として公告を出します。この公告には一定の猶予期間が設けられており、その間に申し出がなければ、正式に無縁墓として扱われます。
無縁墓に指定されたお墓は、石碑や墓誌などが撤去され、墓地から更地のような状態に整地されるのが一般的です。その際、お墓に納められていた遺骨は、他の無縁遺骨とともに合祀墓(ごうしぼ)に移され、合同で供養されます。合祀墓では、個別の供養は行われず、複数の遺骨が一つの墓所にまとめて埋葬されます。
遺骨の移動や供養の方法は管理者によって異なりますが、いずれにしても家族の意向が反映されない形で処理が行われるため、親族にとっては望ましくない結果となるでしょう。
すでにあるお墓が無縁墓になりそうなら「墓じまい」を
お墓を継ぐ人がいない、遠方に住んでいて管理が難しいといった事情がある場合、放置したままにしておくと将来的に無縁墓になってしまう可能性があります。無縁墓になると、墓石が撤去され、遺骨は合祀墓へ移されることになりますが、そこには遺族の意思が反映されません。そうなる前に選択肢として考えたいのが「墓じまい」です。
墓じまいとは、既存のお墓を閉じて遺骨を取り出し、別の場所へ移す手続きのことです。多くの場合は、永代供養墓や納骨堂など、管理の心配がない新しい供養先へ改葬されます。墓じまいをするには、親族間での合意を得たうえで、墓地の管理者や行政機関に必要な書類を提出し、改葬許可を受ける必要があります。
大切な人のお墓を無縁墓にしないためには、「いつか考えよう」ではなく、早めに行動に移すことが重要です。将来に不安がある場合は、専門業者や寺院に相談しながら、墓じまいとその後の供養についてじっくり検討しておくと安心です。
墓じまいの手順については、こちらの記事で解説しています。
墓じまいの手続きと流れを8ステップで解説|費用と必要書類をチェック
お墓を持ちたくない人、墓じまい後におすすめの供養方法
お墓を受け継ぐ人がいない、将来の管理が不安、といった理由から「お墓を持たない供養」を選ぶ人が増えています。現代では、従来の一般墓に代わるさまざまな供養方法が登場しており、それぞれに特徴やメリットがあります。
ここでは、墓じまいを検討している方や、お墓を持たずに供養をしたいと考えている方に向けて、おすすめの供養方法を4つ紹介します。
永代供養
永代供養とは、遺骨をお寺や霊園に預け、寺院や施設が継続的に供養や管理をしてくれる供養方法です。管理費の支払いが不要で、家族に代わって永代にわたり供養される点が大きな特徴です。永代供養には「合祀墓」と「個別墓」の2種類があり、合祀墓は複数の遺骨をまとめて埋葬するタイプ、個別墓は一定期間個別に管理されたのち合祀されることが多いタイプです。
合祀墓は費用が安く管理の手間も不要ですが、一度埋葬すると遺骨を取り出せないデメリットがあります。個別墓は、一定期間は個別に供養してもらえるため、故人への思いを大切にしたい人には安心ですが、合祀墓に比べて費用がやや高くなる傾向があります。
永代供養は、子どもに負担をかけたくない人や、お墓を継ぐ予定のない人、管理不要で費用を抑えたい人に向いている供養方法です。特に「きちんと供養される安心感がほしい」という方におすすめです。
永代供養について詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
永代供養とは?お墓の管理にかかる費用や手間を抑える方法、永代供養墓の選び方
納骨堂
納骨堂は、遺骨を屋内の専用スペースに安置する施設です。ロッカー式・仏壇式・自動搬送式などの形式があります。参拝スペースは空調完備で天候に左右されず、都心部でもアクセスしやすい場所に多く存在します。永代供養が含まれていることもあり、一般墓に比べて費用や維持管理の負担は軽いです。
納骨堂のメリットは、立地の良さと手軽さです。一方で、契約期間が決まっている場合があり、期間終了後は合祀されることがある点はデメリットとして挙げられます。また、建物の老朽化や運営主体の経営状況によっては、将来的に供養が継続できるか不安視されるケースもあります。
納骨堂は「お墓参りのしやすさを重視したい」「屋外の墓地には抵抗がある」「都市部で供養先を探している」といった方に適しています。特に高齢の方や遠方に住む親族がいる場合でも安心して利用できる点が魅力です。
手元供養
手元供養とは、遺骨や遺灰の一部を自宅で保管し、身近な場所で故人を偲ぶ供養の方法です。専用の骨壺やペンダントなどに納めるスタイルがあり、宗教儀式にこだわらない自由な供養として注目されています。費用は比較的安価で、管理や場所の制約もありません。
手元供養のメリットは、いつでも故人をそばに感じられることです。ただし、公的な墓所に埋葬しないため、親族の理解を得づらいかもしれません。また、相続人同士の意見の食い違いや、将来的に遺骨の扱いに困るケースもあります。
手元供養は、「今は遺骨を手放したくない」「お墓という形式にこだわらず、自分の気持ちを大切にしたい」という人に向いています。特に、故人とのつながりを日常の中で感じていたい方に選ばれています。
散骨
散骨は、遺骨を粉末状にして自然に還す供養方法で、海や山などにまく「自然葬」の一種です。法律上の埋葬にはあたらず、節度をもって行えば違法ではありません。費用は他の供養方法と比べて安価で、維持費や管理の必要もありません。
散骨のメリットは、自然に還るという思想や、費用・管理の負担がない点です。一方で、遺骨を回収できないため、後から供養の方法を変えられないことや、親族の理解を得にくいことがデメリットとして挙げられます。また、場所によっては実施できない場合もあります。
散骨は、「自然に還りたい」「形式にとらわれたくない」「自分の死後に家族に負担をかけたくない」と考える人に向いています。宗教や慣習に縛られず、シンプルな旅立ちを望む方に選ばれる供養方法です。
散骨にかかる費用や散骨できる場所について知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
お墓が無縁墓になる前に、墓じまいと改葬を考えよう
お墓を守る人がいなくなれば、いずれそのお墓は無縁墓となり、撤去や合祀といった措置が取られてしまいます。一度無縁墓として処理されると、遺族の意志が介在する余地はほとんどなくなり、故人の供養のかたちも望まぬものに変わってしまうかもしれません。だからこそ、早めに墓じまいと改葬を検討することが大切です。
墓じまいは、新たな供養先を選ぶための前向きな行動でもあります。永代供養や納骨堂、散骨など、現代のニーズに合わせたさまざまな供養方法が整っている今だからこそ、継承という重荷を次世代に残さないための準備を、できるところから始めてみてはいかがでしょうか。
あんしん祭典では提携しているお墓や納骨堂などがあり、永代供養の手配もできます。ほかにも、死後の行政手続きや遺品整理なども承っており、大切な人を亡くした方をトータルでサポートします。
相談は無料なので、まずはお気軽にお電話ください。