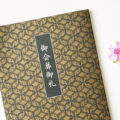家族葬も一般葬と同じく、お通夜を執り行うのが一般的です。本記事では家族葬におけるお通夜の流れや注意点、参列してもらう相手と参列を遠慮してもらう相手に分けた案内状の文例を紹介します。家族葬のお通夜に参列する方や準備する遺族の方に役立つ内容です。
家族葬とは、参列者を近しい親族や親友に限定して執り行う葬儀のことです。規模を小さくすることで費用や準備の負担を抑えつつ、落ち着いた雰囲気で故人を見送れる点が特徴です。その中でもお通夜は、一般葬と同じく大切な儀式として多くの場合に行われます。
しかし、「家族葬のお通夜には誰を呼べばいいのか」「マナーは一般葬と同じで良いのか」と不安に感じる方も多いでしょう。参列者を限定する分、案内の仕方や香典の扱いなどに戸惑う場面も少なくありません。
本記事では、家族葬におけるお通夜の流れや注意点、案内状の文例、参列時のマナーまで詳しく解説します。これから家族葬を執り行う方や、お通夜に参列する予定があり不安を感じている方に役立つ内容です。
家族葬でもお通夜をするのが一般的
家族葬と一般葬の違いは、参列者の人数や葬儀の規模です。儀式の流れやマナー自体に違いはなく、家族葬でも一般葬と同じようにお通夜を行うのが一般的です。家族葬だからといって省略するのではなく、従来の葬儀と同じく、故人を見送る大切な儀式として執り行われます。
ちなみに、現代におけるお通夜は夕方18時頃から21時頃までの時間に行われるのが一般的です。しかし、これは本来の形式とは異なり、「半通夜」と呼ばれるものです。昔ながらのお通夜はろうそくや線香を絶やさず灯し、一晩中故人のそばに寄り添い見守るものでした。故人が再び目を覚ますことを願いながら祈り続けたことが、お通夜の起源とされています。
家族葬のお通夜には誰を呼ぶか
家族葬では参列者をどの範囲まで呼ぶか、何人呼ぶかについて明確な決まりはありません。一般的にはごく近しい親戚や、生前に深く交流のあった友人までに参列者を限定するケースが多くみられます。人数を絞ることで落ち着いた雰囲気の中で故人を見送れるのが家族葬の特徴です。
ただ、参列者の人数の目安を示すなら、5人から30人ほどになるでしょう。次の表は、参列者の人数に応じた「お通夜に呼ぶ人の範囲」の一例です。
| 参列人数 | 呼ぶ範囲 |
| 5人ほど | 一緒に暮らしていた家族のみ |
| 10人ほど | 故人の配偶者と子ども、子どもの配偶者 |
| 20人ほど | 故人の兄弟姉妹やその配偶者、親しかった親戚 |
| 30人ほど | どうぞ、故人の従兄弟や甥・姪、親しかった友人 |
参列者の人数ごとの呼ぶ範囲の一例
お通夜をしない葬儀は「一日葬」と呼ばれる
お通夜をせず、葬儀・告別式だけを1日で執り行う形式は「一日葬」と呼ばれます。最近は高齢化や参列者の負担軽減を理由に選ばれることも増えています。また、お通夜も葬儀・告別式も行わず、火葬炉の前で僧侶に読経をしてから故人を見送る「火葬式」という形もあります。
いずれも費用や準備の手間が少なく、経済的な負担を抑えられる点が大きなメリットです。
しかし、これらの形式では故人と過ごす時間が極端に短くなり、後悔が残ってしまうことも少なくありません。あんしん祭典では、負担を抑えながらも十分なお別れの時間を持てるよう、お通夜を伴う家族葬をおすすめしています。一般葬よりも費用や準備を軽減できるうえ、落ち着いた雰囲気の中で故人を偲び、見送れます。
負担は抑えつつ、しっかりとお別れをしたいと考える方は、まずはあんしん祭典へ気軽にご相談ください。下記のリンクからは、葬儀費用のシミュレーションもできます。
家族葬のお通夜の流れ
家族葬におけるお通夜は、一般葬とほぼ同じ進行で行われます。大切なのは一つひとつの場面で故人に寄り添い、参列者が心を込めて見送れるように準備することです。
会場到着
遺族は参列者よりも早く到着し、受付や供花の配置、焼香の順番などを確認します。開場の1時間前を目安に集合すると良いでしょう。喪主は僧侶への挨拶もこのタイミングで済ませておくのが一般的です。
受付
参列者は受付で芳名帳に記帳し、香典を渡します。家族葬では受付係を親族の中からお願いすることが多く、人数が少ない分、柔らかい雰囲気で対応できます。
お通夜開式
定刻になると司会や葬儀社の進行で式が始まります。僧侶が入場し、遺族と参列者が黙礼をして故人に祈りを捧げます。
読経・焼香・法話
僧侶の読経が続く中、喪主から順に焼香を行います。僧侶から法話がある場合は、故人の人柄や仏教の教えに触れる言葉が語られます。
お通夜閉式
僧侶の退場をもって式は閉じられます。遺族は参列者に一礼し、ここで儀式としてのお通夜は区切りとなります。
通夜振る舞い
式の後には通夜振る舞いが開かれます。料理を囲みながら故人の思い出を語り合う場であり、遺族から参列者へ感謝を示す場でもあります。家族葬では会食をせず、折詰を持ち帰ってもらう形にすることもあります。
解散
通夜振る舞いに参加した参列者は、自分のタイミングで帰宅しても、通夜振る舞いが終わってから帰宅しても構いません。参列者全員が帰宅したあと、遺族だけで翌日の葬儀の流れを再確認しましょう。
家族葬のお通夜に関する注意点・マナー
家族葬特有の注意点やマナーを押さえておくことで、後々のトラブルを防げます。ここでは家族葬で気を付けたいポイント、特に「参列してもらう相手」と「参列を遠慮してもらう相手」に分けた連絡の仕方を解説します。
参列を遠慮してもらう相手にも訃報連絡はする
家族葬で小規模に執り行う場合でも、親族や故人と縁のあった人には訃報を伝えるのが基本です。その際は「家族葬で執り行うため参列はご遠慮ください」と一言添えれば、訃報を知らせつつも参列は辞退してもらえます。
訃報の連絡を葬儀後にしたり、そもそも訃報自体を伝えなかったりすると、後日「なぜ知らせてくれなかったのか」と不満を持たれ、関係に溝ができるかもしれません。
なお、参列を遠慮してほしいと伝えた相手が、「それでも故人に一目会いたい」と訪れることもあり得ます。この場合は快く受け入れて参列してもらうこと、参列してくれたことへの感謝を伝えるのがマナーです。
香典を辞退する場合、その旨を案内状に記載する
家族葬では香典を辞退するケースも多く見られます。辞退する場合は、案内状や訃報連絡の際に「誠に勝手ながら香典は辞退させていただきます」と明記しましょう。
事前に伝えておかないと、香典を持参した参列者に気を遣わせてしまいます。辞退の意向を明確にすることで、受け取る受け取らないといったやりとりを避け、遺族も参列者も儀式に集中できます。
香典辞退の考え方や案内状の書き方は、例文付きでこちらの記事で解説しています。
【例文付き】家族葬の香典辞退の方法|それでも受け取ってほしいと言われたら
家族葬でも遺族は正喪服を着る
遺族は故人を送る立場にあるため、家族葬であっても正喪服を着用するのが一般的です。正喪服とは最も格式の高い喪服で、男性はモーニングコートや黒の礼服、女性は黒無地のワンピースや着物などが該当します。
ただし、お通夜に限っては準喪服を着る場合も珍しくありません。また、家族だけで執り行う小規模なお通夜では、略喪服で対応することもあります。服装の選択は形式に沿うと同時に、場の雰囲気や参列者の立場を考慮することが大切です。
なお、身内だけで家族葬を執り行う場合の服装は、こちらの記事で解説しています。
家族葬の服装はどうする?身内だけの葬儀で失礼しないマナーと注意点
家族葬の案内状の例文
家族葬を行う際には、案内状で参列をお願いする相手と遠慮してもらう相手を分けて伝えることが重要です。ここではそれぞれの例文を紹介します。
参列してほしい相手への案内状
謹啓 〇〇(故人名)儀
令和〇年〇月〇日 永眠いたしました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
つきましては ご多用のところ誠に恐縮ではございますが ご参列賜りますようお願い申し上げます
記
日程:令和〇年〇月〇日(〇曜日)
通夜:午後6時より
葬儀・告別式:翌日 午前10時より
会場:〇〇斎場(住所:〇〇市〇〇町〇丁目〇番)
喪主:〇〇 〇〇
謹白
参列を遠慮してもらう相手への案内状
拝啓
亡 〇〇 儀 〇月〇日〇時 享年〇歳にて永眠いたしましたことを謹んでご通知申し上げます
なお 葬儀は近親者のみの家族葬にて執り行うこととなりました
誠に勝手ながら ご会葬ならびにご香典はご辞退申し上げます。
後日あらためて 生前賜りましたご厚情への御礼を申し上げたく存じますので まずは書中をもちましてご通知申し上げます
謹白
家族葬のお通夜に参列する際のマナー
家族葬に参列する際も、一般葬と同じように基本的なマナーを守ることが大切です。服装や香典の金額、参列の姿勢などに気を配ることで、遺族に対して失礼のない振る舞いができます。
服装のマナー
お通夜に参列する際は、準喪服または略喪服を着用するのが基本です。
喪服には正喪服・準喪服・略喪服の3つの格式があり、正喪服は遺族や喪主が着る最も格式の高い服装です。参列者は準喪服を着るのが一般的で、略喪服は地味なスーツやワンピースを指します。「平服でお越しください」と案内があった場合も、華美でない略喪服を選ぶのが適切です。
男性は黒無地のスーツに白シャツを合わせ、ネクタイ・靴下・靴も黒で統一します。光沢のある素材は避け、ネクタイピンや腕時計などのアクセサリーは控えるのが望ましいです。数珠を持参することも忘れないようにしましょう。
女性は黒のワンピースやアンサンブル、スーツを着用します。ストッキングや靴は黒に統一し、バッグも布製や革製の光沢のないものを選びます。アクセサリーは真珠のネックレスやイヤリング程度にとどめ、真珠でも二連のものや、金具が目立つものは避けます。
子どもは制服があれば制服を着用するのが基本です。制服がない場合は黒や紺、グレーなど落ち着いた色合いの服を選びましょう。靴や靴下も派手な色を避け、全体的に落ち着いた印象になるように整えるのがマナーです。
香典の目安額
香典の金額は、故人との関係の深さや自分の年齢によって変わります。一般的には親族ほど高額になり、友人や知人であれば比較的少額で問題ありません。若い世代よりも社会的立場がある年齢層の方が多めに包む傾向があります。
具体的な目安については、下記の一覧表を参考にしてください。
| 20代 | 30代 | 40代~ | ||
| 親族 | 両親 | 3万~10万円 | 5万~10万円 | |
| 義理の両親 | 3万~5万円 | 10万円 | ||
| 祖父母 | 1万円 | 1万~3万円 | 3万~5万円 | |
| 兄弟・姉妹 | 3万~5万円 | 5万円 | ||
| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万~2万円 | ||
| 従兄弟・その他の親族 | 3,000~1万円 | 3,000~2万円 | ||
| 親族以外 | 上司 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 |
| 上司の家族 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 | |
| 勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 | |
| 社員の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~1万円 | ||
| 友人・知人 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |
| 友人の父母 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |
関係性・年齢に応じた香典の目安額
遅刻しそうでも参列する
葬儀・告別式は厳格な儀式であるため、遅刻は原則として避けるべきです。しかし、お通夜は「急な訃報に駆けつける」という性質を持つため、途中からの参列でも大きな問題にはなりません。
もちろん、定刻に間に合うのが理想ですが、遅れそうだからといって参列自体を諦める必要はありません。30分から1時間程度の遅れであれば、足を運ぶことをおすすめします。
もしそれ以上遅れて式には間に合わなくても、通夜振る舞いに参加できるかもしれません。その際は遅れたことを丁寧に詫び、どうしても故人に一目会いたかったと伝えると良いでしょう。
ただし、20時を過ぎてしまいそうなら無理に参列せず、翌日の葬儀に出席するか、日を改めて弔問するのが望ましいです。
家族葬をお通夜なしにする場合の注意点
家族葬では費用や時間の負担を抑えるために、お通夜を省略して葬儀・告別式だけにすることもあります。ただし、その場合はいくつかの注意点があります。
菩提寺に確認・相談する
菩提寺がある場合は、必ず事前に相談して了承を得ましょう。寺院によってはお通夜を省くことを好まない場合があり、無断で決めると関係が悪化しかねません。
確認を怠ると、法要や納骨を断られるなど後々の供養に支障をきたす恐れがあります。
お別れの時間が短く後悔するかもしれない
お通夜をしない場合、故人と向き合う時間は葬儀当日だけになります。限られた時間では心の整理がつかず、ゆっくり別れを惜しめないこともあります。結果として「もっと一緒に過ごしたかった」と悔いが残るかもしれません。
親族の理解が得られないかもしれない
お通夜は長年の慣習であり、多くの人が執り行うものと考えています。そのため省略すると、親族の中には不満や戸惑いを抱く人が出るかもしれません。
十分に説明をしないと「故人を軽んじているのでは」と誤解され、親族関係にわだかまりを残す恐れがあります。あらかじめ意向を伝え、理解を得ることが大切です。
参列できない人が増えるかもしれない
お通夜は仕事終わりでも参列できる時間帯に設定されることが多く、平日昼間の葬儀よりも参加しやすいです。省略すると、参列の機会を失う人が増えてしまいます。
「最後に一目会いたかった」と思う人の気持ちに応えられず、不満や寂しさを残す可能性があります。周囲の事情も踏まえ、慎重に判断しましょう。
家族葬でもお通夜をするのがおすすめ
家族葬も一般葬も式の流れは基本的に同じであり、どちらもお通夜を執り行うのが一般的です。
お通夜を省略すれば一見費用が抑えられるように思えますが、実際には祭壇や式場使用料、僧侶へのお布施といった費用は発生します。そのため大幅な節約にはなりにくいです。それならば、むしろお別れの時間を十分に持つことの方を大切にしたいものです。心残りのない形で故人を見送ることを、優先してほしいと思います。
あんしん祭典では、お通夜を含む一般的な葬儀の形をおすすめしています。家族葬であれば、一般葬に比べて規模を抑えつつ費用や準備の負担を軽くできます。経済的な負担を意識しながらも、しっかりとお別れの時間を取りたいと考えている方は、どうぞお気軽にあんしん祭典へご相談ください。