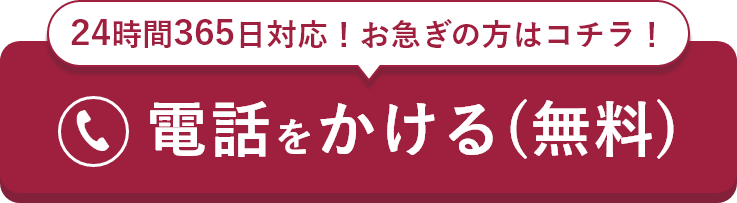認知症の方が作成した遺言書は、無効になるのでしょうか。民法上、どのような基準で判断能力の有無が判断されるのか、家庭裁判所において遺言書の有効性・無効性はどのように判断されるのか。認知症の方が遺言書を作る際の注意点を解説します。
親が認知症でも有効な遺言書は作れるのか、すでに認知症の診断を受けていて遺言書を作成した場合は無効になるのか、と悩む方は多いでしょう。遺言書の有効性を確かなものとするためには、作成時に意思能力や判断能力があるかどうかがポイントになります。
本記事では、認知症と遺言書の関係を法律の観点から解説し、有効な遺言書を残すための具体的な方法を紹介します。
認知症でも有効な遺言書を作れるのか
「認知症と診断されて作成した遺言書は無効になるのでは」と考えている方は多いかもしれません。しかし、実際にはそうとは限りません。遺言書が有効なのか無効なのかを決めるのは病名ではなく、作成時に本人の意思能力や判断能力があるかどうかです。
ここでは、遺言書が有効となるための基本的な条件と、判断の鍵となる「意思能力」について解説します。
遺言書が有効になるための条件
遺言書は、遺言者の自由な意思に基づいて作成されることが前提です。民法第963条では、「満15歳に達した者」が遺言できると定められており、これに加えて意思能力を有していることが必要です。
ここでいう意思能力とは、自分の行為の意味や結果を理解し、判断できる力のことです。つまり、認知症の診断を受けていたとしても、遺言書を作成した際に意思能力が認められれば、その遺言は有効となります。
その一方で、意思能力が欠けている状態で作成した遺言書は、形式を満たしていても無効となります。そのため、遺言書の有効性を判断する際には、作成時に被相続人本人が自分の財産や相続関係を理解していたかが重要なポイントとなります。
また、認知症には段階があり、初期であれば意思能力が十分に保たれていると判断されるケースもあります。本人が冷静に判断できるうちに遺言書を作成しておくことで、将来のトラブルを未然に防げるでしょう。
遺言書の有効性を決める意思能力とは
具体的に意思能力とは、どのような状態を指すのでしょうか。
意思能力とは、自分の行為の意味と結果を理解し、そのうえで判断できる力のことです。遺言書作成の場合、以下のような点を理解できていれば意思能力があると判断されます。
- 自分がどのくらいの財産を持っているかを把握している
- 相続人や受遺者との関係を理解している
- 誰にどの財産をどのように遺すかを自ら判断できる
その一方で、認知症の症状が進んで財産や家族関係を理解できないほど判断力が低下している場合は、意思能力を欠いていると判断され、遺言書が無効になる可能性があります。
家庭裁判所では、遺言書作成時に意思能力があったかどうかが重視され、医師の診断書、介護記録、立ち会い人の証言などをもとに総合的に判断されます。そのため、認知症の方が遺言書を作成する場合は、作成時点の判断力を客観的に証明できる証拠を残しておくことが重要です。
認知症で遺言書が無効になるケース
認知症であっても、遺言書を作成した時点で意思能力があれば、その遺言書は有効になります。ただし、意思能力が欠けた状態で作成した場合や、本人の自由な意思でなかった場合には、遺言書は無効と判断されるケースがあります。
ここからは、実際にどのようなケースで遺言書が無効になるのか、家庭裁判所における判断基準をもとに解説します。
1. 意思能力が失われている場合
もっとも典型的なのが、遺言書作成時に本人が自分の財産や家族関係を理解できない意思能力が欠如している状態だった場合です。認知症が重度に進行していると、財産の内容や相続人の関係を把握できなかったり、誰に何を遺すのかを理解できていなかったりなどの状態に陥ることがあります。このような状態の場合には、意思能力がない判断されます。
医師の診断記録や介護施設での様子から「日常会話も困難」「家族の名前を認識できない」などの記載があると、その方の作成した遺言書は無効と判断されるケースが多いです。
また、認知症の症状は日によって波があります。そのため、作成した日にどの程度の意思能力があったのかも重要になります。そのため、作成当日の診断書や医師の立ち会いがあるかどうかが、後に遺言書の有効性を決める判断に大きく影響します。
2. 家族や第三者による誘導・強要・代筆があった場合
原則、遺言書は本人の自由な意思に基づいて作成されたものでなければいけません。そのため、家族や第三者が内容を誘導したり、本人に無理やり書かせたりした場合は、たとえ形式が整っていたとしても無効と判断されます。
家庭裁判所では、筆跡鑑定や証人の供述などから「本人の意志で書かれたか」を慎重に判断します。自筆証書遺言の場合は、本人が全文・日付・氏名を自筆することが必須条件であり、他人の代筆やパソコン入力されたものは民法上の要件を満たさず無効となります。
3. 検認手続きで無効が発覚した場合
自筆証書遺言を見つけた場合、開封する前に家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。検認とは、遺言書の形式や保管状況を確認する手続きです。ただし、ここで筆跡の不自然さや押印の違和感などが見つかると、偽造や意思能力の欠如の疑いが浮上するケースがあります。
特に、下記のような場合は無効を指摘される可能性が高いです。
- 日付や署名の筆跡が明らかに異なる
- 用紙やインクの違いが複数ある
- 内容が本人の性格や過去の発言と大きく食い違う
検認はあくまでその状態で遺言書が存在していたことを証明する手続きです。しかし、その後の遺言無効確認訴訟につながる重要なきっかけとなります。
認知症でも有効な遺言書を作るための3つのポイント
すでに認知症と診断されている方が有効な遺言書を作成するためにはどうすれば良いのでしょうか。ここからは、認知症と診断された方が有効な遺言書を作成するための3つのポイントをお伝えします。
1. 公正証書遺言を利用する
認知症の方が有効な遺言書を作成するもっとも確実な方法は、公正証書遺言を利用する方法です。
公正証書遺言とは、公証人が本人から内容を聞き取り、その場で遺言書を作成・保管する形式の遺言書です。公証人は、本人の意思確認をしたうえで作成手続きを進めるため、作成時点で意思能力があったことが公的に認められやすく、後に無効を争われるリスクを大幅に減らせます。
さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要な点も大きなメリットです。自筆証書遺言の場合は、発見ご検認手続きが必要です。そのため、その場で筆跡や印影の不自然さが問題になるケースがあります。その一方で、公正証書遺言ならそのような形式的なトラブルを回避できます。
また、公証役場では証人2名の立ち会いが義務付けられており、本人の意思確認が第三者によって客観的に証明される仕組みになっています。認知症の方の場合は、特にこの第三者の立ち会いが信頼性を高める重要な要素になります。
2. 医師の診断書を添付しておく
遺言書を作成した当時の意思能力を客観的に示す証拠として、医師の診断書を取得・添付しておくことをおすすめします。診断書には単に認知症の有無が記載されているだけでなく、「遺言書作成時点で意思疎通が可能であった」「意思能力があった」など、具体的な記載があると効果的です。
特に、次のような文言が診断書に含まれていると、家庭裁判所で有効と判断されやすくなります。
「遺言書作成当日、本人は相続関係および財産内容を理解しており、意思表示を行う能力があったことを確認した。」
このような医学的証明があることで、後に相続人の一部が「意思能力がなかった」と主張しても、有効性を立証する強い根拠になります。診断書を取得する際は、主治医または神経内科・精神科などの専門医に依頼すると良いでしょう。
3. 専門家に立ち会ってもらう
行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に立ち会ってもらうのも、有効な遺言書作成にあたり効果的です。専門家が同席していれば、作成当時の様子や本人の発言内容を客観的に記録でき、「本人の意思で書かれた」という証明になります。
また、専門家は法律的な形式要件にも精通しているため、形式上のミスによる無効リスクも防げます。
さらに、立ち会い時に録音や録画をしておくと、後にトラブルになった際の決定的な証拠として有効です。映像や音声で本人の意思が確認できれば、家庭裁判所でも強い証拠として認められる可能性があります。
認知症でも意思能力があれば遺言書は有効
認知症と診断されていても遺言書を作成した時点で本人に意思能力があれば、その遺言は有効です。ただし、症状の進行や作成環境によっては「意思能力が欠けていたのではないか」「家族が誘導したのではないか」といった疑念が生じ、遺言が無効と判断されるケースも少なくありません。そのため、認知症と診断された後に遺言書を作成する場合は、作成時点で本人の意思が明確であることを証明できる形を整えることが大切です。
あんしん祭典では、遺言書に関する疑問や検認のサポートまで、相続に関わるさまざまな相談に対応しています。法律に基づいた確かな知識と経験をもとに、状況に応じた最適な方法をご提案し、ご家族全員が納得できる形で手続きを進められるよう丁寧にサポートいたします。ご相談は24時間365日無料で対応可能なので、ぜひご相談ください。