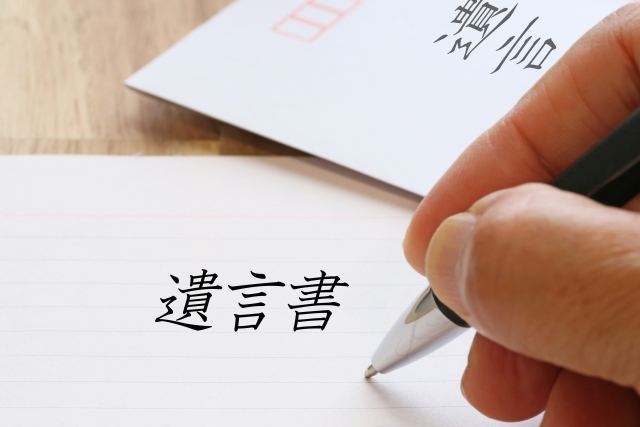法的に有効な遺言書の種類と作成要件、無効になるケースを、自筆・公正証書・秘密証書の違いを踏まえつつ解説します。
遺言書は、大切な財産や想いを次世代に正しく引き継ぐための重要な文書です。しかし、形式や内容に不備があると、法的効力を失い、相続トラブルの原因になる場合もあります。
本記事では、法的に有効な遺言書に必要な要件や、無効を防ぐためのポイントを詳しく解説します。
「遺書」と「遺言書」は違う
日常会話では“遺書”と“遺言書”が混同されがちですが、法律上はそれぞれ全く異なる意味を持ちます。どのような違いがあるのか、解説します。
遺書
遺書とは、一般的には亡くなる前に家族や友人などへ遺す、感謝や想いの言葉、それを綴った手紙を指します。遺言として、自分の亡き後の財産の分け方を指定する人もいるでしょう。
しかし、この意味での遺言に法的な形式や効力はありません。そのため、財産の分け方や相続人の指定などを書いたり口頭で伝えたりしても、法律上は無効となります。
遺言書
民法に基づき、法的効力を持たせるための形式と内容が定められた文書です。
財産の分配方法、特定の人への遺贈、相続人の廃除、未成年者の後見人指定など、法律で認められた意思表示を記載できます。正しい方式と要件を満たしていれば、相続開始時に強い法的拘束力を発揮します。
つまり、“遺書”は想いを伝える手紙、“遺言書”は相続のルールを決める法律文書と覚えておくとわかりやすいでしょう。
遺言書について詳しく知りたい方はこちら
遺言書とはどのような書類?種類や効力、作成のポイントと注意点をわかりやすく解説
遺言書が持つ法的効力
有効な遺言書は、相続の場面で非常に大きな効力を発揮します。遺言書の主な効力には以下のようなものがあります。
財産の分配方法を自由に指定できる
法定相続分と異なる割合で分けたい場合や、特定の財産を特定の人に渡したい場合でも、遺言書で明記すれば原則としてその通りに分けられます。
相続人以外への財産譲渡ができる
遺言書を遺すことで親族などの法定相続人以外の第三者や団体にも、財産を贈れます。
相続人の廃除ができる
事前に家庭裁判所での手続きが必要ではあるものの、遺言書を残すことで、生前に重大な非行があった相続人を遺言によって相続から外せます。
未成年後見人の指定ができる
自分の死亡後に未成年の子どもがいる場合、誰を後見人にするかを決めておけます。
このように、遺言書は単なる最後のメッセージではなく、遺産分割の方向性を決定づけ、相続トラブルを防ぐための強力な法的ツールなのです。
法的に有効な遺言書の種類と特徴
遺言書には、法律で定められた方式があります。この方式を守らないと、どんなに本人の意思が明確でも法的効力が認められません。民法上の方式は、大きく普通方式遺言と特別方式遺言に分けられます。それぞれどのような方式なのか解説していきます。
普通方式遺言
日常的に作成されるのは、以下の3つの普通方式遺言です。それぞれの特徴・メリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言書とは、遺言者が自ら全文・日付・氏名を手書きし、押印して作成する最もシンプルな方法です。財産目録はパソコン作成や通帳コピー添付も可ですが、各ページに署名押印が必要です。
2020年7月より自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局での保管が可能になりました。これにより、検認が不要になり、紛失や改ざんのリスクも大幅な減少が期待できます。
【メリット】
- 紙とペンがあれば作成可能、費用はほぼかからない
- 誰にも知られずに作成できるため、プライバシーを守りやすい
- 自分の都合で何度でも書き直せる
【デメリット】
- 法的要件をひとつでも満たしていないと無効
- 紛失・改ざんのリスクが高い
- 相続開始後、原則として家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局保管の場合は不要)
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、原本を保管する方式です。遺言者が希望の内容を伝え、公証人が筆記・読み聞かせをし、遺言者と証人2名が署名押印します。
不動産や預貯金など多額の財産を持っていたり、相続人間の関係が複雑で争いの火種があったりして、確実に有効な遺言を残したい場合に適しています。
【メリット】
- 形式不備のリスクがほぼない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんのリスクがない
- 相続開始後、検認不要ですぐに執行できる
【デメリット】
- 公証人手数料、証人謝礼などの費用がかかる(財産額によって数万〜十数万円)
- 証人2名の立会いが必要
- 遺言書作成時に、内容が公証人・証人などの第三者に知られる
公正証書について詳しく知りたい方はこちら
公正証書遺言の手続き方法|本人と相続人が知るべきメリット・デメリットや相場費用
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られずに作成し、封印した状態で公証役場に持ち込み、方式だけ確認してもらう方法です。署名押印した文書を封筒に入れ、封印のうえで公証人と証人2名が確認します。
遺言の存在は確実に残しつつ、生前は内容を誰にも知られたくない場合に適しています。ただし、近年ではあまり活用事例がなく、形式不備のリスクもあるため、自筆証書遺言や公正証書遺言の活用が良いでしょう。
【メリット】
- 内容を完全に秘密にできる
- 公証役場で日付と存在を証明してもらえる
【デメリット】
- 形式不備があっても公証人は内容に関与しないため、無効の可能性あり
- 相続開始後に検認が必要
- 実務上は利用例が少ない
特別方式遺言
特別方式遺言とは、普通方式が使えない特別な状況下でのみ認められる方式です。以下の2種類の方式が主な特別方式遺言です。特別方式遺言はあくまで緊急時の例外であり、可能な限り普通方式での作成が推奨されます。
危急時遺言
危急時遺言とは、病気や事故などで死期が迫っており、公証人を呼ぶ時間がない場合に、証人3人以上の立会いで口頭により作成できます。作成後20日以内に家庭裁判所の確認が必要です。
【参照】民法976条
隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、船舶内や離島など、公証人の利用が困難な場所にいる場合に認められる方法です。
【参照】民法977条
法的に有効な自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば作れる手軽な方式ですが、民法で定められた形式要件をひとつでも満たしていないと無効になります。法的に有効な自筆証書遺言を作成するための要件と注意点を詳しく解説します。
遺言者が全文を自筆する
遺言の本文はすべて遺言者本人が手書きで書く必要があります。代筆やパソコン入力は認められません。2019年の法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー、不動産登記事項証明書の添付が可能になりました。ただし、目録の全ページに遺言者の署名と押印が必要です。
財産が多い場合は、目録だけを別紙にして添付すると書きやすく管理もしやすくなります。手書き本文と印刷目録を混在させる場合は、漏れがないかよく確認しましょう。
日付を正確に記載する
遺言書には作成日を特定できる形で記載する必要があり、日が特定できない書き方は無効となります。
西暦でも和暦でも大丈夫ですが、すべて統一して書くのが望ましいです。遺言書を書き直す際は、必ず新しい日付を記載しましょう。
氏名を自筆で記載する
遺言者の氏名は必ず手書きで書きます。苗字だけや名前だけでも無効になることはありませんが、必ず本人が特定できるように書かなければなりません。このとき、ゴム印や印刷、代筆することはできません。
押印
遺言書には押印が必要です。法的には認印でも有効ですが、実印を使い、印鑑登録証明書を添付しておくとより信憑性の高さが確保されます。
また、捺印の位置は氏名の下や余白など明確にわかりやすい場所が望ましいです。シャチハタは使用できないので、注意しましょう。
訂正の手続き
遺言書の一部を訂正する際は、訂正箇所に二重線を引き、訂正の旨を明記し、署名・押印する必要があります。訂正方法を誤ると訂正は無効となり、訂正前の文書の通りに解釈されます。
遺言書の法的効力が発生するタイミング
遺言書は作成直後から効力が発生するわけではありません。遺言書に法的に効力が発生するのは、遺言者が亡くなった瞬間からです。生前に遺言の内容を強制的に実行させることはできず、本人はいつでも遺言を撤回・変更できます。
【参照】民法1022条
無効となる主な5つのケース
有効な遺言書にするためには、不備がないように注意しなくてはいけません。無効となる主なケースを5つご紹介します。
| 形式的要件の不備 | ・自筆証書遺言で全文を自書していない ・日付が特定できない記載 ・氏名や押印が漏れている ・訂正が正しくされていない |
| 遺言能力の欠如 | 遺言を作成するには、満15歳以上で意思能力がある必要があります。 認知症が進行して判断能力を失っている状態で作成した遺言は無効になる可能性があります。作成時に医師の診断書を添付することで、有効性を確保できます。 |
| 公序良俗に反する内容 | 特定の相続人への極端な差別など、法律や社会秩序に反する内容を記載した場合、その部分が無効とされる可能性があります。 |
| 遺留分を侵害している | 遺言で財産の全てを特定の人に譲れます。ただし、他の相続人が遺留分侵害額請求をすれば、侵害された部分については返還義務が生じます。 |
| 強迫・詐欺による作成 | 脅迫やだまされて作成した遺言は、取り消せます。 |
法的に有効な遺言書を作成し思いを確実に遺そう
遺言書は、形式要件を満たして初めて法的効力を持つ重要な文書です。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の方式には、それぞれメリットとデメリットがあり、財産の内容や相続人の関係性によって適した方法は異なります。
遺言書を作成するにあたり重要なのは作るだけでなく、確実に執行される状態にしておくことです。遺留分や相続トラブルのリスクも考慮し、必要に応じて司法書士や弁護士など専門家の助言を受けながら作成すれば、次の世代に想いと財産を確実に届けられます。
あんしん祭典では、遺言書に詳しい司法書士をご紹介しています。法的に有効な遺言書の作成で迷うことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。