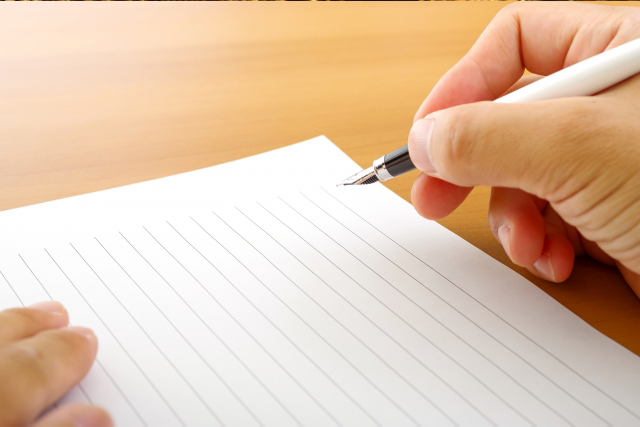香典返しとは、いただいた香典への感謝を品物でお返しすることです。香典返しにはお礼状を添えるのが基本です。本記事では宗教別・ケース別の文例や注意点を紹介します。家族葬で香典返しとお礼状の対応に迷う方に役立つ内容です。
香典返しとは、いただいた香典への感謝を伝えるために品物を贈ることです。そして、その際には感謝の気持ちを添えるお礼状を書くのが一般的です。
しかし、家族葬のように規模を抑えた葬儀では「本当に香典返しは必要なのか」「お礼状には何を書けばいいのか」と迷う方も少なくありません。しかし、近しい人のみの集まる小さな葬儀だからこそ、失礼のない対応を心がけたいものです。
本記事では、宗教別・ケース別の香典返しに添えるお礼状の文例と、言葉選びの注意点を紹介します。家族葬を執り行った方やこれから準備を進める方に向けて、安心してお礼状を書けるように解説しています。
家族葬でも香典返しは必要
家族葬と一般葬の違いは参列者の人数や規模にあります。葬儀の流れやマナーは変わらないため、家族葬でも香典返しを用意することが必要です。小規模な葬儀であっても、参列や香典への感謝を伝える心配り、つまり香典返しは欠かせません。
香典返しとは、いただいた香典に対して感謝の気持ちを品物でお返しすることです。渡し方にはお通夜や葬儀当日にその場で渡す「即日返し」と、四十九日法要後にまとめて渡す「後返し」があります。地域や慣習によって形式は異なるため、事前に確認しておくと安心です。
香典返しの品物は、いただいた香典の3分の1から半額程度を目安に選びます。お茶やお菓子、日用品など実用的で消耗できる品がよく選ばれます。感謝の気持ちを込めつつ、相手に負担をかけない品を選ぶことが大切です。
香典返しの選び方やおすすめの品については、こちらの記事で解説しています。
香典返しの金額や品物は?挨拶状の書き方、送る時期【おすすめ4選】
香典返しにはお礼状を添える
香典返しを後返しで送る場合、品物と一緒にお礼状を添えるのが一般的です。お礼状には、お通夜や葬儀の際にいただいた弔意への感謝と、無事に四十九日を終えたことの報告を簡潔に書き添えます。長文にする必要はなく、感謝の気持ちが伝われば十分です。
一方、即日返しの場合はその場で直接手渡すため、お礼状は不要です。ただし、四十九日法要を終えて忌明けを迎えた際に、改めて挨拶状を送ると丁寧な対応となります。地域の習慣や家族の意向を踏まえ、相手に配慮した方法を選びましょう。
【宗教別】香典返しに添えるお礼状の例文
香典返しに添えるお礼状を書く際は、宗教に則った言葉選びをしなくてはなりません。仏教・神道・キリスト教それぞれに沿った文例を知っておくことで、失礼のない対応ができます。ここでは、宗教別に例文を紹介し、その後に注意すべき言葉選びのポイントも解説します。
仏教
謹啓
先般はご多用のところ ご会葬賜り誠にありがとうございました
ご焼香を賜り 故人も心安らかに旅立つことができたことと存じます
令和◯年◯月◯日 四十九日の法要を相営み 無事に忌明けを迎えることができました
これもひとえに 皆様の温かいご厚情の賜物と深く感謝申し上げます
本来であれば拝眉のうえ直接ご挨拶申し上げるべきところ 書中にてお礼を申し上げますことを 何卒ご容赦ください
つきましては 心ばかりではございますが 供養の印の品をお届けいたしますので ご受納くださいますようお願い申し上げます
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主〇〇 〇〇
言葉選びの注意点(仏教)
仏教では故人が成仏し仏に成ることを前提とするため、「ご冥福を祈ります」や「成仏」などの言葉を使います。その一方で「昇天」や「安らかに眠る」などは仏教以外で用いられる表現のため避けましょう。
なお、浄土真宗では「安らかにお眠りください」の代わりに、「お浄土よりお導きください」という表現が使えます。
神道
謹啓
このたびは故母 〇〇帰幽に際しまして 御弔意ならびに御玉串料を賜りまして 厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして令和◯年◯月◯日 五十日祭の儀を滞りなく相済ませ 忌明けを迎えることができました
生前に賜りましたご厚情にも 深く感謝申し上げます
本来であれば拝眉のうえご挨拶申し上げるべきところ 書中にて御礼を申し上げますことを何卒ご容赦ください
つきましては偲草の品をお届けいたしますので ご受納賜りますようお願い申し上げます
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主〇〇 〇〇
言葉選びの注意点(神道)
神道では死を「穢れ」と捉えるため、仏教で使う「成仏」や「冥福」といった言葉は用いません。代わりに「安らかに鎮まる」「御霊の安寧」などの表現を使うのが適切です。また香典は「玉串料」や「御榊料」と記すのが一般的で、お礼状でもこれらの言葉を用いましょう。
なお、例文で使っている「偲草の品」とは、香典返しの品のことです。偲草とは故人を偲び追慕するという思いを粗品に代えてという意味で、神式やキリスト教式で使われます。
キリスト教
謹啓
このたびはご丁重なる御花料を賜り 心より御礼申し上げます
おかげをもちまして 令和◯年◯月◯日 追悼ミサを無事に終えることができました
生前中に賜りましたご厚情を深く感謝申し上げます
本来であれば拝趨のうえ直接お礼を申し上げるべきところ 書中をもちましてご挨拶とさせていただきます
つきましては偲草の品をお届けいたしますので ご受納賜りますようお願い申し上げます
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主〇〇 〇〇
言葉選びの注意点(キリスト教)
キリスト教では仏教や神道で用いる「成仏」「冥福」などの表現は不適切です。代わりに「安らかに眠られるようお祈りいたします」や「平安が与えられますように」といった言葉を使います。また香典は「御花料」と表記し、お礼状でも同じ言葉を用いるのが一般的です。
宗派による違いにも注意が必要です。プロテスタントでは「召天」という言葉を用い、故人が神のもとに召されたことを表します。 一方カトリックでは「帰天」という表現が用いられます。
【ケース別】香典返しに添えるお礼状の例文
香典返しに添えるお礼状は、相手との関わり方や状況によって文面を変える必要があります。会葬に来られなかった方や香典返しを辞退された方など、さまざまなケースに応じた表現を知っておくことで、丁寧で失礼のない対応ができます。
会葬はなく、香典だけいただいた場合
謹啓
このたびはご丁重なる御香典を賜り心より御礼申し上げます
おかげをもちまして令和◯年◯月◯日 四十九日の法要を無事に相済ませ 忌明けを迎えることができました
本来であれば直接お目にかかり御礼を申し上げるべきところ 書中にてご挨拶申し上げますことを何卒ご容赦ください
つきましては供養のしるしの品をお届けいたしますので ご受納賜りますようお願い申し上げます
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主〇〇 〇〇
香典返しを辞退された場合
謹啓
このたびはご丁重なる御香典を賜り 厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして 令和◯年◯月◯日 四十九日の法要を滞りなく相済ませ 忌明けを迎えることができました
本来であれば供養の品をお届けすべきところ 過分なお心遣いにより辞退のお申し出をいただきましたので ここに謹んで御礼申し上げます
本来であれば直接お目にかかり御礼を申し上げるべきところ 書中にてご挨拶申し上げますことを何卒ご容赦ください
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主〇〇 〇〇
1つの文面で対応したい場合
会葬の有無や香典返しの辞退など、相手に応じて文面を分けたくない場合は、次の例文が参考になります。
謹啓
このたびはご多用のところ 故人のためにご厚情を賜り心より御礼申し上げます
おかげをもちまして 令和◯年◯月◯日 四十九日の法要を滞りなく相済ませ 忌明けを迎えることができました
本来であれば直接お目にかかり御礼を申し上げるべきところ 書中にてご挨拶申し上げますことを何卒ご容赦ください
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
謹白
令和〇年〇月〇日
喪主〇〇 〇〇
会葬の有無や香典返しの品について書かないのがポイントです。ただ、香典返しの辞退という厚意に対してきちんとお礼するといった、個別具体的な内容のお礼状にした方が丁寧なのは確かです。香典返しの辞退があった場合は、その相手だけでも個別でお礼状を書くと良いでしょう。
「印刷会社に頼むため、文面が2つあるとその分費用がかさむ」のような場合は、香典返しの辞退をした相手にだけ自分で印刷する、手書きでお礼状を書くなどするのがおすすめです。
香典返しに添えるお礼状を書くときの注意点
香典返しに添えるお礼状は、宗教や地域の習慣に配慮しながらも、基本的なマナーを押さえることが大切です。形式を守ることで相手に誠意が伝わり、失礼のない文面になります。ここでは、お礼状を書く際に特に注意したいポイントを解説します。
内容は簡潔に、便せん1枚にまとめる
お礼状は長文にせず、感謝の言葉と法要を終えた報告を簡潔にまとめます。便せん1枚に収めることで、相手に負担をかけずに気持ちが伝わります。
冗長な文章になるとわかりにくくなるだけでなく、便箋が2枚になることで「不幸が重なること」を連想させてしまいます。
薄墨ではなく黒墨で書く
香典返しに添えるお礼状は、香典を受けたことへの感謝を伝える文書です。そのため、香典の表書きと異なり、薄墨ではなく黒墨を用いるのが正しい作法です。
薄墨は弔事の場で急な悲しみを表す際に使うもので、お礼状にはふさわしくありません。
忌み言葉や重ね言葉を使わない
お礼状では、不幸が重なることを連想させる言葉や、縁起が悪いとされる表現を避けます。これらは忌み言葉・重ね言葉と呼ばれ、弔事では使ってはいけません。また、生死を直接表現する言葉も、やわらかな表現に置き換えましょう。
忌み言葉
忌み言葉は「切る」「終わる」など、死や別れを直接的に連想させる表現です。「忙しい」も、「亡」の字が入っているため避けるべきです。お礼状にはついつい「お忙しい中」と書いてしまうようになりますが、「ご多用の中」のように置き換えましょう。
| 避けるべき表現 | 言い換え |
| 切れる、途絶える | ご縁が途絶えることなく → 今後もご縁をいただけると |
| 離れる | 離ればなれになる → ご一緒できなくなる |
| 終わる | これにて終わりとなります → これをもちまして一区切りといたします |
| 追って | 追って連絡いたします → 後日連絡いたします、あらためて連絡いたします |
| 忙しい | お忙しい中 → ご多用の中 |
忌み言葉の例と言い換え
重ね言葉
重ね言葉は「たびたび」「ますます」など同じ言葉をくり返す言葉、「再び」のようにくり返しを意味する言葉です。不幸が繰り返されることを連想させるとして、不吉とされています。
| 避けるべき表現 | 言い換え |
| たびたび | よく、いつも など |
| ますます | いっそう、さらに など |
| 重ね重ね | 改めて、いくえにも など |
| くれぐれも | どうぞ、ご無理のないように など |
重ね言葉の例と言い換え
生死を直接表現する言葉
「急死」「死亡」「生存」「生きていた頃」といった生死をそのまま表す言葉は、次のようなやわらかい表現に置き換えましょう。
【”死”に関する言い換え】
- 逝去
- 旅立つ
- 突然のこと
【”生”に関する言い換え】
- 生前
- 元気だった頃
頭語・結語はセットで使う
「拝啓」や「謹啓」などの頭語を用いた場合は、「敬具」や「謹白」などの結語を必ず添えます。文の形式を整えることで、礼を失しない書面になります。
なお、香典返しのお礼状では「謹啓」と「謹白」のセットを使うのが基本です。「謹啓」と「謹白」でセットなので、「謹啓」と「敬具」のような、間違った組み合わせをしないよう気を付けましょう。
季節の挨拶を付けない
お礼状には、通常の手紙で用いる季節の挨拶は不要です。弔事の文面では、故人と香典への感謝に焦点を当てるのが基本です。
句読点を付けない
香典返しのお礼状は、昔からの習慣に倣い、句読点を付けないで書きます。文の区切りは改行や適度な空白で整えます。
句読点を使うと文章が途切れ、縁が切れることを連想させるため、不吉とされています。
追伸を付けない
お礼状に追伸は不要です。必要な内容は本文にまとめ、追加の一文は避けましょう。
葬儀とは関係のない近況報告がしたい、相手の様子を知りたいといった場合には、追伸を付けるのではなく、お礼状とは別に手紙を送ります。
家族葬でも香典返しとお礼状は必要!例文を参考に文面を作ろう
家族葬は規模を抑えた葬儀であって、流れやマナーは一般葬と変わりません。参列や香典への感謝を伝えるために、香典返しとお礼状を送るのも、一般葬と同じです。
お礼状を書く際は、宗教や相手の状況に合わせた言葉を選び、簡潔で丁寧な文面に整えることが大切です。本記事で紹介した例文を参考に、状況に合ったお礼状を作りましょう。
香典返しの品選びやお礼状の書き方に迷う方は、あんしん祭典までお気軽にご相談ください。あんしん祭典では葬儀はもちろん、その後の法要、急に必要になった返礼品の手配なども承っています。
その他、行政手続きのサポートや遺品整理の相談など、できることは多岐にわたります。相談は無料なので、まずは気軽にお電話いただければ幸いです。