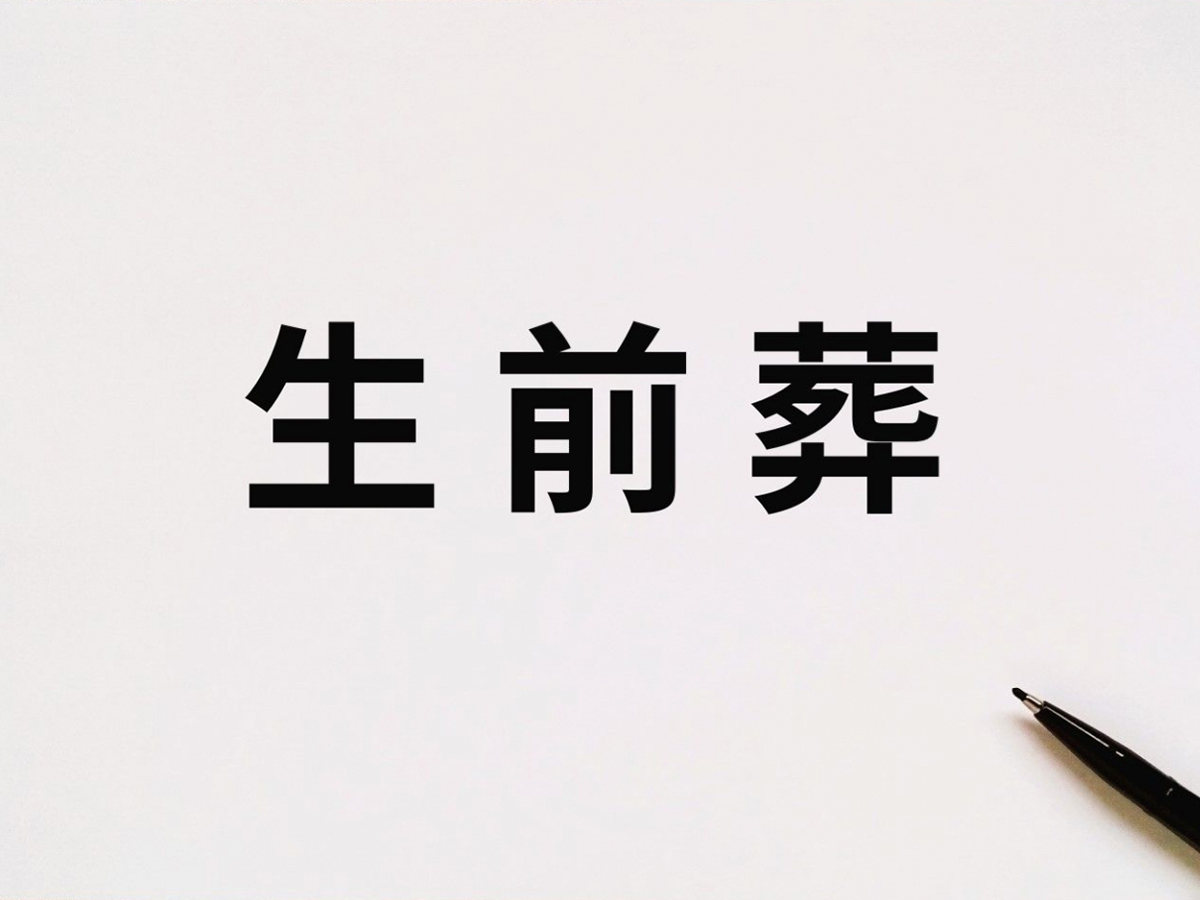生前葬とは、生きているうちに自分のためにする葬儀のことです。本記事では生前葬の流れや費用、注意点までわかりやすく解説します。終活を考え始めた方や、自分らしい最期を考えている方におすすめの記事です。
生前葬とは、本人が生きているうちに自らのためにする葬儀のことです。従来の葬儀とは異なり、感謝を直接伝える場として開かれることが多く、自由な形式で行えるのが特徴です。
「自分の思いをきちんと伝えられるうちに式を開きたい」「家族に負担をかけたくない」――そんな気持ちを抱いている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、生前葬の意味や流れ、費用相場、注意点までをわかりやすく解説します。終活を意識し始めた方や、自分らしい最期のかたちを考えたい方に向けて、役立つ情報を丁寧にお伝えします。
生前葬とは
生前葬とは、本人が生きているうちに自らのために葬儀することです。亡くなったあとに開く一般的な葬儀とは異なり、主役である本人が出席し、参列者と直接会って感謝の気持ちを伝えられるのが特徴です。
自分らしい形で人生の節目を演出できる点でも注目されており、最近では「人生の卒業式」といった意味合いで行われることもあります。宗教儀式としてではなく、形式にとらわれない自由なスタイルで開かれるケースが多いのも特徴です。
一般的な葬儀との違い
最大の違いは、本人が存命のうちに式をする点です。一般的な葬儀では、亡くなった後に遺族が喪主となって準備や対応を担いますが、生前葬では本人が主導して企画を進めます。
また、亡くなった方を悼むのではなく、これまでの人生をねぎらい、感謝や思いを伝え合うことが主な目的です。形式も比較的自由で、宗教儀式を伴わないお別れ会のようなスタイルも多く見られます。
涙を流すよりも、笑顔で語り合うような雰囲気になることが多く、明るい雰囲気で行われる点でも通常の葬儀とは異なります。
なぜ生前葬する人が増えているのか
少子高齢化や核家族化が進む中で、従来の葬儀の在り方に疑問を持つ人が増えています。家族に負担をかけたくない、自分が希望する形で見送られたいと考える人にとって、生前葬は柔軟な選択肢となっています。
また、「感謝を伝えたい人に、元気なうちに会っておきたい」という思いも背景にあります。自身の人生の区切りを自分で演出できることに価値を見出し、生前葬を前向きな節目と捉える傾向も広がっています。
生前葬するメリットとデメリット
生前葬には、自分の思いをかたちにできる自由さや、感謝を直接伝えられる喜びがあります。一方で、費用や周囲の理解といった面で迷いを感じる方もいるかもしれません。
ここでは、生前葬することによる代表的なメリットとデメリットについて、具体的に見ていきます。
生前葬のメリット
最大の魅力は、自分らしいかたちで人生の節目を演出できることです。一般的な葬儀では宗教や地域の慣習に従う場面が多いですが、生前葬であれば演出や進行、会場の雰囲気まで、すべて本人の希望に沿って自由に決められます。
また、直接「ありがとう」を伝えられるのも大きなメリットです。故人となってからでは伝えられない感謝の気持ちを、生きているうちに自分の言葉で届けられます。参列者にとっても、感謝を受け取ったり、お礼を返したりできる貴重な機会になります。
さらに、葬儀後の遺族の負担を軽減できる点も見逃せません。亡くなったあとに準備や手配に追われることがなくなるため、家族にとっても心の整理がしやすくなるケースがあります。
生前葬のデメリット
生前葬には注意すべき点もあります。まず挙げられるのが費用の負担です。生前に葬儀をした場合でも、亡くなった後に改めて簡単な葬儀を開くことは多く、火葬もしなければなりません。そのため、通常よりも費用がかさむ可能性があります。
また、周囲の理解を得にくいという面もあります。とくに高齢の親族や、伝統的な考えを重んじる方にとっては「縁起が悪い」と受け止められてしまうこともあります。せっかくの感謝の場が誤解を生まないよう、事前の説明や配慮が必要です。
本人にとっては意義があっても、すべての人がその価値を理解してくれるとは限りません。実施にあたっては、周囲の気持ちにも目を向けることが大切です。
生前葬の流れと準備すること
生前葬には、ある程度の準備期間が必要です。どのような進行にするのか、誰を呼ぶのか、どこで開くのかなど、決めておくべき項目は多岐にわたります。
ここでは、生前葬の一般的な流れや、準備時に検討すべきポイントを紹介します。
生前葬の一般的な流れ
生前葬の流れに明確な決まりはありませんが、多くの場合は以下のような順で進められます。まず、開催の趣旨や日程を決め、その後、会場や司会者、演出内容を検討します。
当日は、開式の挨拶に続いて、本人からのメッセージや来賓のスピーチが行われることが多く、映像の上映や思い出話の共有なども交えながら進行します。形式ばった進行よりも、和やかな雰囲気の中で会話や交流を楽しむスタイルが好まれる傾向にあります。
式が終わった後には、軽食を交えて歓談の時間を設けたり、記念品を手渡したりして、ゆるやかに閉式となります。
式場や司会の手配
生前葬の会場としては、葬儀会館のほか、ホテルの宴会場やレストラン、地域の公民館などが選ばれることがあります。宗教儀式がない場合は、必ずしも葬儀専用の施設にこだわる必要はありません。
会場を選ぶ際は、アクセスの良さや収容人数、雰囲気などを考慮し、参加者が集まりやすい場所を選ぶことが大切です。費用や設備面については、事前に見積もりをとって比較検討しておくと安心です。
司会はプロに依頼することもあれば、本人の希望で親しい友人や家族にお願いすることもあります。進行役によって式の雰囲気が大きく左右されるため、自分の意図をしっかり伝えておくことが大切です。
招待客の決め方
誰を招くかは、生前葬の雰囲気や目的によって異なります。親族や親しい友人、長年お世話になった仕事関係者など、これまでの人生で深く関わった人たちを中心に考えるのが一般的です。
多くの人を招く必要はありません。あくまで本人が「会っておきたい」「感謝を伝えたい」と思う人に来てもらうことが優先されます。中には、少人数で落ち着いた場を好む人もいます。
招待の連絡は、はがきやメール、電話など状況に応じた方法で構いません。ただし、趣旨を正しく伝えないと誤解を招く可能性があるため、「生前葬であること」「お別れの会として気軽に来てほしいこと」などを明確に伝えるよう心がけましょう。
服装や演出の決め方
服装については、喪服ではなく平服での参加を促すことが一般的です。暗く重い雰囲気にしたくないという本人の意向から、カジュアルな服装や明るい色の装いが勧められることもあります。
演出についても自由度が高く、映像や音楽、スライドショーなどを取り入れる方が増えています。本人がこれまでどんな人生を歩んできたのかを振り返るような演出や、笑顔になれるような工夫がよく見られます。
特定の宗教色を避ける場合は、献花や黙祷などの代わりに、メッセージカードや花束の贈呈などで想いを表現するケースもあります。大切なのは、本人が心から納得できる内容にすることです。
生前葬の費用相場と内訳
生前葬を検討する際、費用がどの程度かかるのかは多くの方が気になるポイントです。内容や規模によって金額は大きく異なりますが、一般的な内訳や相場感を知っておくことで、無理のない計画が立てやすくなります。
ここでは、生前葬にかかる主な費用項目や、通常の葬儀との比較、費用を抑えるための工夫についてご紹介します。
式場・演出・飲食などの費用項目
生前葬の費用は、主に会場費・演出費・飲食費などで構成されます。会場費は式を開く場所によって異なり、葬儀会館やホテル、レストランなどの使用料がかかります。施設によっては控室や音響設備の使用料が別途必要になることもあります。
演出費には、映像やスライドショーの制作、司会者や演奏者の依頼料、装花や演出小物などが含まれます。特に本人のこだわりが反映されやすい部分であり、内容によって費用が大きく変動します。
飲食費は、立食形式の軽食からコース料理までさまざまです。人数に応じて総額も変わるため、招待客の規模と合わせて検討する必要があります。このほか、記念品や返礼品の準備費用もかかることがあります。
通常の葬儀と比較して高い?安い?
生前葬の費用は内容によって幅がありますが、30万円〜を目安に考えると良いでしょう。豪華な演出や多人数を招いた場合は、さらに高額になることもあります。
一方、通常の葬儀では、式場費・祭壇費・火葬料・僧侶へのお布施・料理・返礼品などを含めて100万〜200万円程度かかるのが一般的です。こうして比べると、生前葬そのものの費用は抑えめですが、亡くなった後に簡易的な葬儀や火葬の必要がある点には注意が必要です。
つまり、生前葬する場合、通常の葬儀に加えてもう一つセレモニーを設けることになるため、合計費用としてはやや高くなる傾向があります。
費用を抑えるための工夫
費用を抑えるには、式の規模を見直すことが効果的です。招待人数を絞ることで、会場の広さや飲食の量を抑えられます。また、規模にあった会場を選ぶことでコストダウンも可能です。例えば、公民館や地域の集会所などを活用すれば、使用料を大幅に抑えられることもあります。
演出についても、プロへの依頼を最小限に留め、映像や音楽を自作したり、司会を知人に依頼したりすることで、無理のない範囲でオリジナリティを出せます。
さらに、葬儀社や専門業者に複数の見積もりを取り、内容を比較することも大切です。プラン内容と費用のバランスを見ながら、自分に合ったかたちを選ぶことで、満足度の高い生前葬が実現できます。
生前葬の注意点
生前葬は自由な形式で行える一方で、事前に気をつけておくべき点もいくつかあります。とくに家族や親族との関係性、宗教・地域の風習、法律上の確認事項などは見落とせません。
ここでは、生前葬を円滑に実施するために注意すべきポイントについてご紹介します。
家族や親族の理解を得る方法
生前葬を企画するうえで、家族や親族の理解を得ることは非常に重要です。本人の希望であっても、周囲に驚きや戸惑いがあると、気持ちよく送り出してもらえない可能性があります。
まずは、自分がなぜ生前葬をしたいのか、その理由や思いを丁寧に説明することが大切です。「感謝を直接伝えたい」「葬儀で家族に負担をかけたくない」といった前向きな理由であれば、理解されやすくなります。
家族と十分に話し合ったうえで、開催時期や内容についても相談し、なるべく皆の納得が得られるよう調整を進めましょう。理解者を一人でも得ておくことで、実際の準備もスムーズに進みやすくなります。
宗教や風習との関係
生前葬は宗教的な儀式を伴わない自由な形式で行われることが多いですが、宗教や地域の風習との兼ね合いを無視することはできません。とくに親族の中に信仰心の深い方がいる場合には、抵抗感を持たれることもあります。
「生前に葬儀をするのは縁起が悪い」と考える方もいますが、宗派や住職によって考え方はさまざまです。僧侶の参加を希望する場合は、事前に相談して理解を得ることが大切です。
また、地域によっては風習や習慣が根強く残っていることもあります。地元で開催する場合は、近隣の目や受け止め方についても配慮しておくと安心です。
法的な制限
生前葬そのものには、法律上の制限はありません。本人の意思で自由に開催できます。ただし、式で扱う内容や後続の手続きに関しては、注意が必要です。
たとえば、生前葬の場で遺言に関する話をする場合は、法的に有効な遺言書を残しておく必要があります。口頭で伝えた内容が法的効力を持つわけではないため、注意しましょう。
また、生前葬とは別に、死亡届の提出や火葬の申請など、亡くなった際に必要な手続きは通常通り発生します。生前葬をしたからといって、これらが免除されることはありません。葬儀後の流れもふまえて、家族と連携をとっておくことが大切です。
生前葬に向いている人・そうでない人
生前葬は、すべての人にとって最適な選択肢とは限りません。価値観やライフスタイル、家族との関係性などによって、向き不向きがあります。
ここでは、生前葬を前向きに検討しやすい人と、慎重に考えるべきケースについて見ていきましょう。
生前葬が向いているケース
生前葬は、次のような考えを持っている人に適しています。
- 自分の人生の節目を自らの手で演出したいと考えている
- お世話になった人たちに直接感謝を伝える場を持ちたい
- 家族に葬儀の負担をかけたくないと思っている
- 宗教や形式にとらわれず、自由なスタイルの式を望んでいる
- 闘病中で終活の一環として準備を進めている
こうした思いを持っている方であれば、生前葬は前向きな選択肢となり、自分らしいかたちで人生を締めくくるきっかけになります。
生前葬が向いていないケース
一方で、以下のような状況にある場合は、生前葬の実施に慎重になったほうがよいかもしれません。
- 家族や親族が強く反対している、または理解が得られていない
- 宗教や地域の慣習により、生前の葬儀をタブーとする風潮がある
- 死後の葬儀もしたいが、費用の負担は抑えたい
- 心身の状態が安定しておらず、準備を進める余裕がない
生前葬は自由な選択肢である一方、周囲との関係や環境によっては、かえってストレスや摩擦を生む可能性もあります。無理に行おうとせず、自分の気持ちと向き合いながら判断することが大切です。
生前葬は、生きているうちに感謝を伝える新しい葬儀の形
生前葬は、亡くなったあとではなく、生きているうちに自らの思いをかたちにできる新しいかたちのセレモニーです。これまでの人生を振り返り、大切な人たちに「ありがとう」を直接伝えられる貴重な機会でもあります。
従来の葬儀とは異なり、宗教や形式にとらわれず、自分らしさを大切にした自由な演出ができるのも大きな魅力です。その一方で、費用や周囲の理解といった現実的な課題もあるため、じっくり検討しながら準備を進めることが大切です。
誰にとっても「人生の最期」は避けて通れないものですが、その迎え方は人それぞれです。生前葬は、感謝とともに人生を締めくくる前向きな選択肢のひとつとして、これからますます注目されていくでしょう。