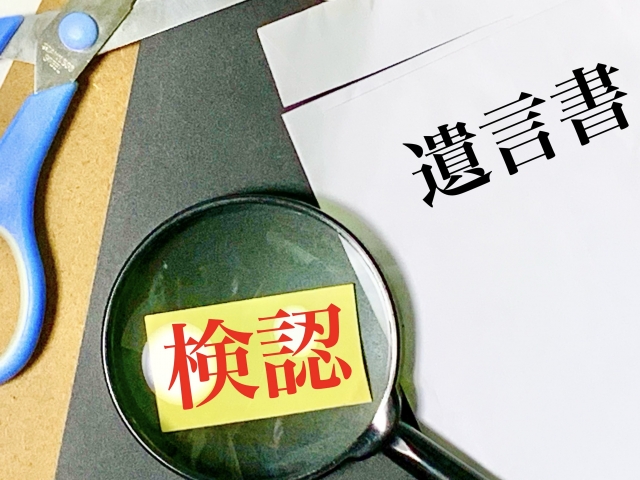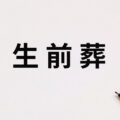遺言書に必要な検認とは何なのでしょうか。手続きの流れや必要書類、かかる時間・費用などをわかりやすく解説します。
「遺言書を発見したけど、どうすればいいの?」、そんな疑問を持つ方が増えています。特に、検認という言葉に馴染みがないと、その後どのように手続きを進めるべきか不安になるでしょう。
本記事では、遺言書を家庭裁判所に提出する検認の意味や手続きの流れ、かかる時間・費用、必要書類などを丁寧に解説します。相続トラブルを避けるためにも、検認制度の理解は重要です。遺言書を発見した方、これから遺言書を作成する予定の方も、ぜひ参考にしてください。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、遺言書が本当に遺言者によって書かれたものかを裁判所が形式的に確認する作業です。家庭裁判所が行う手続きで、遺言書の存在や内容、日付、署名、印などを確認し、それを公的に記録します。
検認では、遺言書に記載された内容が法律的に正しいかどうか、その内容が公平かどうかといった点までは審査されません。あくまで、「遺言書が改ざんされていないか」「きちんと存在していたか」を確かめ、家庭裁判所が事実を公文書として記録することが目的です。遺言の有効・無効そのものを判断する手続きではありません。
| 遺言書の種類 | 検認の必要の有無 |
| 自筆証書遺言 | 必要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
| 法務局保管制度を利用した遺言書 | 原則不要 |
検認が必要な理由
遺言書は、相続に関する非常に重要な意思表示です。
しかし、自筆の場合、遺言書の内容が本当に故人の意思のもと書かれたものなのか疑念が生まれやすいです。検認とは家庭裁判所が公的な場で遺言書の内容を確認し、手続きとして記録を残すことで、このようなトラブルを未然に防ぐために行われます。
相続人同士の仲が良好でない場合や、財産の配分に偏りがある場合は、特に遺言書の存在そのものがトラブルの火種になりがちです。検認することで遺言書がどのように遺されていたのか証拠が残ります。そのため、相続人の間での信頼性を担保しやすくなるのです。
検認の手順
遺言書の検認は、家庭裁判所に遺言書を提出すれば終わりというわけではありません。検認には、正確な申立てと必要書類の準備が求められます。
検認の手続きの流れと準備すべき書類を詳しく解説します。
検認に必要な書類
申立てに必要な書類は、主に以下です。準備する書類に漏れがあると受理までに時間がかかるため、慎重に揃えましょう。
- 遺言書の原本(封印されたまま)
- 検認申立書(裁判所サイトや窓口で入手可能)
- 遺言者の出生から死亡まですべての戸籍謄本(親子関係や配偶者の確認のため)
- 相続人全員の戸籍謄本(相続関係を明らかにするため)
【参照】裁判所|遺言書の検認
検認の申立ては家庭裁判所へ
検認の申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。先述の必要書類を、管轄の家庭裁判所の窓口に持参するか郵送することで、提出します。
提出書類の様式や連絡用の切手代は、家庭裁判所によって異なる場合があります。そのため、事前に公式サイトで確認しておくと安心でしょう。
検認は相続人が行う
検認の申立ては、遺言書を発見した相続人や、その他の利害関係人(受遺者など)が行います。相続人が複数人いる場合、代表して1名が申立てをすれば足ります。
また、遺言書の内容によっては、相続人でない第三者が遺産の一部を受け取るケースもあります(受遺者)。その場合も、利害関係人として申立てが可能です。
検認の申立て後の流れ
検認の申立てが受理されると、1〜2週間ほどで裁判所から検認期日通知書が届きます。検認期日通知書は相続人全員に送付される、検認が行われる日程、場所、持参物などが記載されている書類です。
検認への出席は任意ですが、検認期日通知書を受け取った相続人はなるべく参加するのが望ましいです。出席できない場合は、事前に出席できない旨を裁判所に連絡しましょう。
検認当日の流れは下記です。
- 家庭裁判所にて出席者確認
- 遺言書の開封
- 裁判官による内容確認と読み上げ
- 書面化(検認済証明書の発行)
これらの4つの手続きを経て、遺言書の検認が完了します。検認後は検認済証明書を交付してもらったのちに、相続手続きへ進めるようになります。
検認が完了するまでの期間
検認手続きは、一般的に申立てから1〜3ヵ月程度の期間を要します。
相続人の人数が少なくスムーズに書類を用意できると、裁判所の混雑具合にもよりますが1ヵ月ほどで検認が完了します。ただし、期日は裁判所によって組まれます。申請後どれほど期間を要するかはコントロールできないため、運次第になります。
数ある提出書類の準備に時間がかかったり、相続人が多く通知に時間を要したりする場合、検認には2~3ヵ月かかることもあるでしょう。
検認完了までを短くするには、どれだけ早く必要書類を揃えられるかが重要です。早めの準備と裁判所とのスムーズなやり取りが、検認完了までの期間を短縮する大きな要因となります。
検認手続きにかかる費用
検認にかかる費用は主に以下のとおりです。
| 項目 | 費用 | 備考 |
| 収入印紙代 | 800円/1通 | 家庭裁判所に納める手数料 |
| 郵便切手代 | 数百円~1,000円程度 | 裁判所から相続人に通知を送るための切手 |
| 戸籍謄本・住民票取得費 | 450円~750円/1通 | 相続人や遺言者の戸籍を取得する際に、市区町村役場で支払う費用 |
専門家に依頼する場合の費用
遺言書の検認の申請は、司法書士や弁護士に依頼できます。専門家に依頼した場合の費用の相場は下記です。
| 依頼先 | 費用目安 |
| 司法書士 | 約3万円~8万円 |
| 弁護士 | 約5万円~10万円以上 |
専門家に依頼すると、戸籍の取得や申立書作成、裁判所への連絡などを一括で任せられます。そのため、時間を節約したい方や相続人間でのトラブルが不安な方は専門家に依頼する方がスムーズに進められるでしょう。
ただし、専門家に依頼しても裁判所に支払う印紙代・切手代などの実費は別途かかります。トータルでかかる費用については、あらかじめ確認しておきましょう。
封印された遺言書を勝手に開封するのはNG
遺言書を見つけたら、すぐに中身を確認したくなるかもしれません。しかし、特に自筆証書遺言を発見した場合、検認しないまま開封したり、使用したりすることはできません。自筆証書遺言や秘密証書遺言が封筒に入って封印されていた場合、その封を家庭裁判所での検認前に勝手に開けることは法律で禁止されています。
【参照】民法1004条|遺言書の検認
また、封印のない遺言書であっても相続手続きに勝手に使うのは違法です。検認を受けずに遺言書を開封してしまった場合、相続人は5万円以下の過料に処される可能性があります。
さらに、検認が済んでいない自筆証書遺言では、銀行口座の解約や不動産の名義変更などの相続手続きが進められません。つまり、検認は法的にも実務的にも、必ず踏まなければならない最初の手続きなのです。
遺言書を見つけたら、まずは検認
遺言書を発見した際、検認の必要性を理解して動けるかどうかが、相続手続きをスムーズに進める大きな鍵となります。自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封したり、検認を経ずに相続手続きをしたりすると、過料のリスクや相続人間のトラブルに発展する可能性があります。
相続人の立場からすると、遺言書の検認は煩わしく思えてしまうかもしれません。しかし、遺言書の検認は故人の意思を尊重し、公正な相続を実現するために欠かせない手続きです。一連の申請や手続きに不安がある方は、司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
あんしん祭典では遺言書の検認にも詳しい司法書士を紹介しています。遺言書を見つけたら慌てて開封せず、検認の必要性を正しく理解してから行動しましょう。