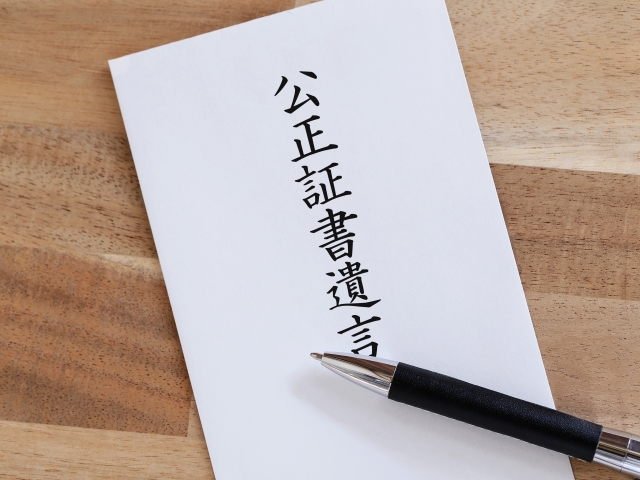遺言書があれば遺産分割協議書は不要なのでしょうか。遺言書と遺産分割協議書の違いや、必要・不要となる条件、実際に協議書が求められるケースまで分かりやすく解説します。
遺言書があれば遺産分割協議書はいらないと思っている方は少なくないでしょう。実際には、遺言書の内容や相続人の同意状況によって、協議書が必要になるケースもあります。
本記事では、遺言書と遺産分割協議書の違いを整理しつつ、遺言書がある場合に協議書が不要となる条件や、逆に作成が必要となる具体的なケースを解説します。
そもそも遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた財産の分け方を文書化したものです。被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合や、遺言書があっても一部の財産について記載がない場合に作成されます。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式の移管など、相続手続きを進める際に提出が必要になるケースが一般的です。金融機関や法務局で相続人全員が合意した証拠として扱われます。
遺言書との違い
遺産分割協議書よりも耳にする機会が多い遺言書ですが、どのような違いがあるのでしょうか。
相続人全員で話し合って決めた財産の分け方が書かれている遺産分割協議書に対して、遺言書は被相続人が生前に自らの意思で財産の分け方を指定した書面です。遺言書の場合、相続人の合意は必要ありません。遺言書が法的に有効で、財産の分配が明確に記載されている場合、その内容が優先されます。
| 遺言書 | 被相続人の意思を反映する文書 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の合意を反映する文書 |
また、遺言書は作成者の死後に初めて効力が発生します。その一方で、遺産分割協議書は相続開始後に相続人同士で作成します。そのため、遺言書の有無次第で、遺産分割協議書が必要かどうかが変わります。
遺言書があれば遺産分割協議書が不要になる
条件を満たした遺言書があれば、遺産分割協議書が不要となります。遺産分割協議書が不要となるのは、以下の3つの条件を満たしている場合に限ります。相続人の話し合いで相続の配分などを決められたくない方は、以下の条件を満たした遺言書を作成できるよう十分に注意してください。
1.法的に有効な遺言書を作成する
遺言書は、民法で定められた形式を満たしていなければ無効となります。有効な遺言書には、以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自筆し、押印までする)
- 公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する)
- 秘密証書遺言(内容を秘匿しつつ公証役場で存在を証明する)
確実に執行したいのであれば、公証役場で公証人が作成する公正証書遺言が安心です。
手軽に残したいのであれば、自筆証書遺言が良いでしょう。ただし、2020年7月以降開始された自筆証書遺言保管制度の利用がおすすめです。この制度では法務局に遺言書を預けられます。利用すると検認が不要になり、より安全に利用できます。
法的に有効な遺言書について詳しく知りたい方はこちら
法的に有効な遺言書とは?無効化されないためのポイントを解説します
2.全財産の分け方を明確に記載する
遺言書に財産の一部しか記載がない場合や、誰が何を相続するのかが曖昧な場合は、残りの財産について別途協議が必要になります。すべての財産の相続先を自身で決めたい場合は、以下の3点が遺言書内で明確に記載されているか十分に確認してください。
- 不動産・預貯金・株式など、すべての財産について受取人が特定されている
- 財産の名称や所在地、口座番号などが正確に書かれている
- 「全財産を⚪︎⚪︎に相続させる」など包括的な指定がされている
このように、追加で話し合う必要がないほど明確な指定があれば、協議書を作成する理由がなくなります。
3.相続人全員に遺言内容に従うことを同意してもらう
仮に有効な遺言書があっても、相続人の誰かがその内容に異議を唱えれば、話し合いが必要になります。
全員が遺言書の内容通りの相続に同意すれば、そのまま遺言書をもとに手続きを進められます。特に公正証書遺言の場合は、偽造や変造の心配がなく、相続人間の信頼性も高く保てます。そのため、遺産分割協議書が不要となる可能性が高まります。
遺言書があっても遺産分割協議書が必要になるケース
有効な遺言書があっても、必ずしも遺産分割協議書が不要になるわけではありません。以下のような場合は遺産分割協議書の作成が必要になるケースが多いため、注意しましょう。
1.遺言書の記載が不十分な場合
遺言書の中で財産の一部しか相続先が指定されていない場合、残りの財産については相続人全員で話し合う必要があります。遺言書に不動産の相続先だけ記載され、預貯金や株式について触れられていない場合、記載されていない分をどう分けるかを協議し、協議書にまとめます。
2.記載の解釈が分かれる場合
「長男に家を相続させる」とだけ書かれている場合、敷地は含まれるのか、家具や家財はどうするのかなど、細かい点で意見が分かれるケースがあります。このような曖昧な表現がある場合は、解釈の相違をなくすために協議書で詳細を定める必要があります。
3.遺言の対象外の財産がある場合
遺言書作成後に新たに取得した財産や、書き漏れた財産がある場合、その分については遺産分割協議が必要になります。特に被相続人が複数の口座や不動産を持っていた場合、把握漏れが生じやすいため注意が必要です。
4.遺留分の侵害が発生している場合
遺言書の内容が、法律で保障された最低限の相続分である遺留分を侵害している場合、該当する相続人は遺留分侵害額請求ができます。請求が認められると、遺言の内容をそのまま実行できなくなります。なお、遺留分は遺留分侵害請求をした人に対して、金銭で支払わなくてはなりません。
遺留分について詳しく知りたい方はこちら
遺言書と遺留分を徹底解説!最低限の取り分と請求方法・対策まで完全ガイド
5.相続人全員で遺言内容を変更したい場合
遺言書があっても、相続人全員の合意があればその内容を変更して別の分け方ができます。この場合は、新しい合意内容を遺産分割協議書として作成し、相続手続きに進みます。
6.遺言書が無効と判断された場合
遺言書が民法上の要件を満たしていなければ無効となり、最初から遺言書がないのと同じ扱いになります。例えば自筆証書遺言で日付や署名、押印が欠けている場合は無効となるため、特に注意が必要です。このような不備や無効が発生した場合には、相続人全員で遺産分割協議により、協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する流れ
遺言書が不十分であったり、相続人全員で内容を変更したりする場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書を作成する手順は下記のとおりです。
1.相続人の確定
まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、誰が法定相続人かを確定します。さらに、相続人全員の現在の戸籍謄本も揃えて漏れなく相続人を特定し、後から知らなかった相続人が現れるリスクを防ぎます。
2.相続財産の調査・一覧の作成
遺産分割協議をするためには、分ける財産を正確に把握する必要があります。そのために、各財産にどれほどの価値があるのか証明書を揃えておくと、正確です。
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税評価証明書 |
| 預貯金 | 残高証明書、通帳コピー |
| 株式・投資信託 | 証券会社からの残高報告書 |
| その他 | 車、貴金属、借金など |
3.協議内容の話し合い
相続人全員で集まり、各相続人の希望や生活状況を踏まえて財産の分け方を話し合います。話し合いは一度で終わるとは限らず、複数回行われるケースもあります。特に不動産を誰が取得するか、代償金を支払うかなどはこのタイミングで細かく決定しましょう。
4.協議書の作成
合意内容を文章にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。遺産分割協議書には、以下の情報を記載します。
- 被相続人の氏名
- 被相続人の死亡日
- 相続人の氏名と住所
- 各財産の分配方法
- 日付
改ざん防止のため、ページをまたぐ場合は契印(ページをまたぐ際、両ページにまたがって押すハンコ)しましょう。
5.各種手続きで協議書を利用
作成した遺産分割協議書は、不動産登記、預貯金の解約・移転、株式の名義変更などで提出します。各機関で原本確認を求められることが多いため、必要部数をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。
6.保管と将来のための備え
遺産分割協議書は、手続き完了後も5年以上保管しておくことをおすすめします。相続税の申告や、後から財産が見つかった場合に参照する可能性があるためです。
有効な遺言書があれば遺産分割協議書は不要な場合もある
遺言書があれば、遺産分割協議書を作らずに相続手続きを進められる場合があります。ただし、有効な遺言書がある、全財産の分け方が明確、相続人全員が同意しているという3つの条件を満たしたときに限ります。これらの条件のいずれかを満たしていないと、たとえ遺言書があっても協議書の作成が必要になります。
相続は一度きりの大切な手続きです。遺言書の内容や状況に不安がある場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家へ相談し、トラブルのない円滑な相続を目指しましょう。そのためには、安心して相談できる司法書士や弁護士を見つけることが重要です。あんしん祭典では、相続関連の実績を多数持つ専門家を紹介してもらえます。